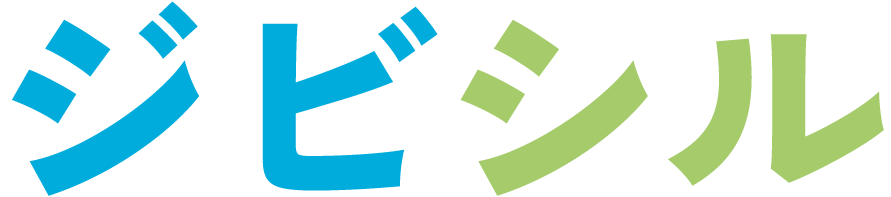「がま腫ってなに?」「自然に治る?」「悪性の可能性は?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今回はがま腫の原因や放置のリスクについて詳しく解説します。
- がま腫の原因は唾液腺の損傷
- ほっとくと再発や感染のリスクあり
- ごく稀に悪性の腫瘍と鑑別が必要
放置しても大丈夫と思われがちですが、早期の受診と治療が大切です。詳しく見ていきましょう。
がま腫(粘液嚢胞)の主な症状

最も多い舌下型ガマ腫は、舌の下にゼリー状の膨らみが現れます。また、顎下型ガマ腫は、顎の下に軟らかいふくらみとして触れます。痛みはないことがほとんどですが、ときに、食事や会話の際に違和感が出現します。大きくなると3~4cmほどに達します。
がま腫(粘液嚢胞)の原因・なりやすい方
がま腫は、舌下腺や顎下腺からの唾液が導管の損傷や閉塞により漏れ出し、組織内に袋状にたまること(嚢胞)で発症します。10代〜30代の若年層に多く、口内の外傷や繰り返す炎症がきっかけとなることがあります。
がま腫(粘液嚢胞)の検査/診断の方法
視診と触診でおおよその診断が可能ですが、超音波検査やMRIを行うこともあります。針を刺し、嚢胞の内容液を検査に出すこともあります。
がま腫(粘液嚢胞)治療方法・回復期間の目安

治療は、保存治療と手術治療があります。保存治療は、OK-432という薬剤を嚢胞内へ注入する方法で、硬化療法と呼ばれます。炎症を引き起こし、嚢胞を癒着・縮小させる効果があります。特に嚢胞が大きくない場合や初回発症では、外来での硬化療法が推奨されます。
硬化療法は、日帰りでの処置が可能で、一過性に発熱や発赤・痛みを伴うことがあります。1回の治療で治ることもありますが、2~3回繰り返し注入を必要とすることも多いです。再発例や効果が乏しい場合には、手術療法として、舌下腺の摘出が検討されます。病院の方針により異なりますが、入院治療となることが一般的です。
類似症状の疾患
粘液嚢胞、皮様嚢胞、顎下腺腫瘍などが類似症状として挙げられます。
がま腫(粘液嚢胞)にならないための予防・日頃のケア
- こまめな手洗い・うがいを心がける
- 免疫力を下げないように十分な睡眠とバランスの良い食事を摂る
- 加湿器を使用し、乾燥を防ぐ
- 喫煙を控える(受動喫煙にも注意)
さいごに
がま腫は良性疾患ではありますが、ごくまれに悪性疾患が隠れている可能性もあるため、違和感を感じたら早めに耳鼻科を受診しましょう。正しい診断と早期治療で安心して日常生活を送ることができます。