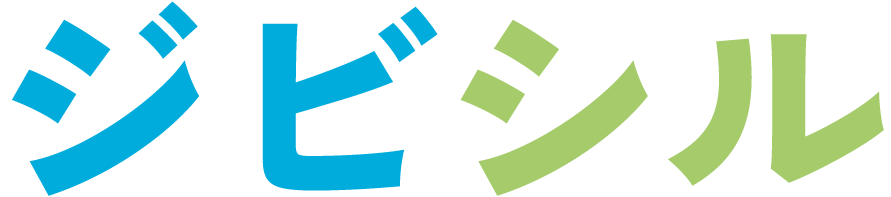食事や水で「むせる」、長引く「咳」。年齢のせいと放置すると誤嚥性肺炎の原因に。
どの病気が隠れるか、何科へ行くか、検査・治療や漢方まで要点をまとめます。
POINT
- 食事中のむせる・水で咳は要注意
- 姿勢調整でむせ予防、検査は外来可
- 体質に合わせ漢方も併用可
症状の「原因」を見極めると、治療はぐっと楽になります。
まずは何科?→耳鼻咽喉科で内視鏡を含む評価を受け、再発しにくい生活と治療計画へつなげましょう。
目次
嚥下障害(誤嚥)の主な症状
- 水やお茶でむせる/むせやすくなった
- のどにつかえる感じ、飲み込みに時間がかかる
- 食後・就寝前後に咳や痰が増える(後鼻漏・逆流で悪化)
- 声がかすれる、むせと同時に声が出しづらい
- 繰り返す発熱・痰増加(誤嚥性肺炎のサイン)
- 家族に「1食で2回以上むせている」と指摘される
- サラサラの飲料で特に咳き込みやすい
嚥下障害(誤嚥)の原因・なり易い方

主因は嚥下機能の低下(加齢、脳卒中やパーキンソン病など)。
鼻炎・副鼻腔炎による後鼻漏、声帯麻痺・喉頭疾患、逆流性食道炎などの病気も原因になります。
高齢者、口腔乾燥、服薬の副作用、フレイル、早食い・ながら食事、就寝直前の飲食はリスク。
乾燥期や花粉の季節は悪化しやすく、痰や咳が増えむせやすくなります。
まず受診すべき何科か迷う場合は、のどの専門・耳鼻咽喉科が入口です(外来での評価とトリアージが推奨)。
嚥下障害(誤嚥)の検査/診断方法
- 嚥下内視鏡検査(FEES/VE):鼻から細い内視鏡で咽頭・喉頭を観察し、着色水やゼリーで嚥下を評価。外来で実施でき、その場で所見共有が可能。軽度の喉頭流入の有無や代償手技の効果確認に有用です。
- 嚥下造影検査(VFSS):必要時に専門外来へ紹介し、口腔〜食道の動態をX線透視で解析。食道入口部の開大不全など、FEESだけでは分かりにくい点を評価します。
- リスクの見極め:喉頭流入後にしっかりむせる(喀出できる)方は外来フォロー可。一方、むせられない“サイレント”誤嚥が疑われる場合や神経学的所見があれば、総合病院の嚥下専門外来や神経内科へ。
嚥下障害(誤嚥)の治療方法
リハビリテーション(言語聴覚士中心)
- 顎を引く「顎引き嚥下」:気道防御・喉頭閉鎖・食道入口部開大を高め、軽度の喉頭流入にまず試す頭位。
- 頸部回旋:片側声帯麻痺などで誤嚥を減らすのに有効。咽頭クリアランス向上が期待。
- メンデルゾーン手技/舌圧トレーニング:嚥下動態を改善するための定型訓練として用います。
- Shaker訓練:頭部挙上の等尺性・等張性運動を6週間。機器不要で一般外来に適します。
薬物治療
- 後鼻漏・副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎を治療し、刺激性の咳や痰を抑える。逆流が強い場合は胃酸抑制薬。
漢方(医師の体質評価の上で)
- 乾いた咳・のど乾燥に麦門冬湯、冷え・水様性鼻汁に小青竜湯、のどのつかえ感に半夏厚朴湯など。
嚥下障害(誤嚥)の回復期間の目安

- 後鼻漏が主因:2〜4週でむせる・咳が軽快しやすい。
- 姿勢・訓練中心:4〜8週で日常のむせ半減を目標。
- 声帯麻痺など器質的要因:処置後1〜3か月で機能改善を期待(個人差あり)。
※訓練導入時はリスク説明と同意が重要です。
類似症状の疾患
逆流性食道炎、咳喘息・気管支喘息、COPD、薬剤性の咳(ACE阻害薬など)、気道異物、気管支拡張症、マイコプラズマ・百日咳、喉頭アレルギー、心不全など。長引く咳(8週以上)、血痰、体重減少、発熱を伴う場合は至急受診。
嚥下障害(誤嚥)にならないための予防・日頃のケア
- 食事は顎を軽く引く・一口量を小さく・よく噛む(外来で効果確認が可能)
- 水・お茶は一気飲みを避け、姿勢調整(顎引き/頸部回旋)を状況に応じて併用
- 就寝3時間前までに食事を終え、逆流対策(枕を高く)
- 毎食後の歯磨き・口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防
- 声出しや軽い体操で口・舌・のど周りを温めてから食事
さいごに
「むせる」「咳が続く」は、見逃したくないサインです。
耳鼻咽喉科では、外来で可能な嚥下内視鏡検査に基づき、姿勢指導からリハビリ、薬物療法、必要時の専門紹介まで一貫して対応します。何科か迷ったら、まずはのどの専門へ。
患者さんの生活に合わせ、無理のない計画で安全に“口から食べる”力を取り戻すお手伝いをします。