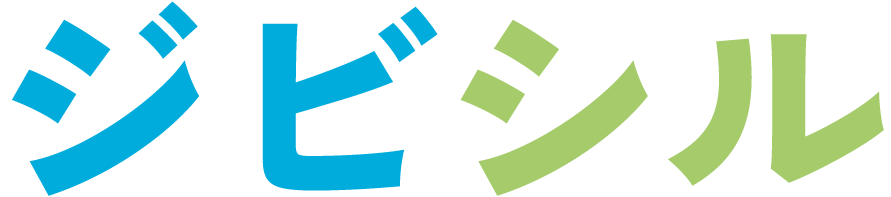クループ症候群は息の通り道がせまくなり、咳や喘鳴(ゼイゼイ)、呼吸困難をひきおこす病気です。子どもに多く、まれに大人もかかることがあります。特に、咳がなかなか治らないときは注意が必要です。どのような症状が出るのか、詳しく解説していきます。
- クループ症候群は子供に多く、まれに大人にも発症することがある
- 咳が長引く場合やゼイゼイと音がする場合は注意が必要
- 大人では重症化する場合もあり注意を
クループ症候群の主な症状
クループ症候群の主な症状は、「犬が吠えるような咳」が特徴的です。夜間に悪化することが多く、ゼーゼーとした呼吸(喘鳴、stridor)が見られることもあります。また、声がかすれる、喉が痛む、発熱、場合によっては突然の呼吸困難を伴うこともあります。特に、大人の場合は風邪と勘違いしやすいため、症状が長引く場合は注意が必要です。
クループ症候群の原因・クループ症候群になり易い方

クループ症候群はウイルス感染が主な原因で、パラインフルエンザウイルス、RS ウイルス、インフルエンザウイルスなどのウイルス感染が最も一般的です。免疫力が低下していると発症しやすく、特に6か月から3歳までの幼児に多く見られ、秋から冬にかけて流行することが多いです。保育施設や家庭内での感染が広がりやすいです。また子どもだけでなく、大人でも過労やストレスで免疫が落ちていると感染しやすくなります。
こどもは大人より息の通り道が小さいため、声門下(喉の奥の方)が狭くなりやすいと考えられています。
クループ症候群の検査・診断の方法
診察では、咳の音や呼吸の状態を確認し、喉頭の炎症を観察します。咽喉ファイバー検査(喉の内視鏡検査)を行うことで、声帯や気道の腫れを確認できます。場合によっては、血液検査やX線検査が実施されることもあります。
診断は他の疾患を除外することも重要で、感染のほかに小児では異物誤飲(ボタン電池や小さなおもちゃなど)との鑑別が重要です。
クループ症候群の治療方法・回復期間の目安
クループ症候群の治療は、症状の重症度によって異なります。軽症の場合は、自宅で加湿や水分補給を行いながら様子を見ます。重症の場合は、入院の上でステロイド薬や吸入薬を使用することもあります。また、呼吸困難がある場合は、酸素吸入や入院治療が必要になることもあります。回復期間は個人差がありますが、軽症であれば3~5日程度、重症の場合でも1週間~10日程度で回復することが一般的です。
クループ症候群の類似症状の疾患
- 急性喉頭蓋炎
- 急性気管支炎
- 喉頭炎
- 百日咳
- インフルエンザ
- 異物誤嚥・誤飲
クループ症候群にならないための予防・日頃のケア

- こまめな手洗い・うがいを心がける
- 免疫力を下げないように十分な睡眠とバランスの良い食事を摂る
- 加湿器を使用し、乾燥を防ぐ
- 喫煙を控える(受動喫煙にも注意)
さいごに
クループ症候群は軽度の場合、家庭での対処が可能ですが、呼吸困難が強くなる場合や唇が青白くなるなどの症状が出た際は、すぐに医療機関を受診することが重要です。特に夜間に症状が悪化することが多いため、注意深く見守る必要があります。家族や保育施設での感染拡大を防ぐために、早期の受診と予防対策が大切です。