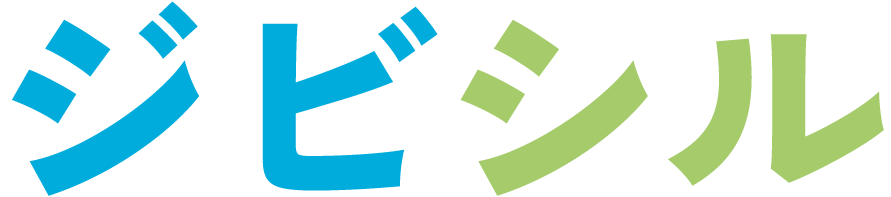「舌が回らない」「言葉がはっきりしない」「寝ているときにいびきがうるさい」といった悩みがある方は、もしかすると舌小帯短縮症が原因かもしれません。中には手術が必要な場合もあります。
- 滑舌が悪い原因のひとつに舌小帯短縮症がある
- いびきや睡眠の質にも影響することも
- 専門的なトレーニングで改善可能な場合もあるが、手術も選択肢となる
滑舌やいびきなど、日常生活に影響する症状があれば、舌小帯の異常を一度疑ってみましょう。
舌小帯短縮症の主な症状

舌小帯短縮症の方は、「さしすせそ」「らりるれろ」などが発音しづらく、滑舌が悪くなることがあります。また、舌を出したときにハート型になったり、上にうまく持ち上がらなかったりすることも特徴です。
構音障害は全体の30%以上にみられ、特にサ行とラ行が多く影響を受けます。
さらに、就寝中に舌の位置が安定せず、いびきをかく原因になる場合もあります。発音や滑舌が悪いだけでなく、乳児では哺乳がうまくできないこともあり、成長段階によってさまざまな症状が現れます。
舌小帯短縮症になり易い方
舌小帯短縮症は先天的なもので、生まれつき舌の裏側にある「小帯」が短い、あるいは硬いことで起こります。いくつかの型があり、重度の舌小帯短縮症では単に小帯が短いだけでなく、舌の発育不全(舌自体が短い)がみられる可能性があります。また、遺伝的な要素もあると考えられています。
乳幼児期に気づかれないまま成長すると、発音の問題や口腔機能の低下に繋がります。滑舌に不安を感じるお子さんや、いびきの強いお子さんには注意が必要です。
舌小帯短縮症の検査/診断の方法
診断は、耳鼻咽喉科や口腔外科、小児科などで視診を中心に行います。舌の動きや形を確認し、必要に応じて咽喉ファイバーを使うこともあります。
特に幼児では発音や哺乳の様子をチェックすることが重要です。診察時間は10〜15分程度で、簡単に判断できることが多いです。専門医によるチェックをおすすめします。
治療の方法・回復期間の目安
治療法には2つあり、軽度の場合は舌の可動域を広げるトレーニング(筋機能療法)を行います。発音や舌の位置を改善するための専門的な指導が受けられ、通常2〜3ヶ月で効果が期待できます。年齢が上がるにつれて自然と可動域も広がるため、年齢による経過観察も重要です。
重度の場合や改善が乏しい場合には「舌小帯切除術(簡単な外科手術)」が選択されます。研究では、4歳以上での手術が望ましいとされており、手術後は数日で日常生活に戻れるケースがほとんどです。
なお、3歳以下では成長に伴って自然に改善することもあるため、慎重に経過観察されることもあります。
舌小帯短縮症の類似症状
口蓋裂、発達性構音障害、睡眠時無呼吸症候群など

舌小帯短縮症にならないための予防・日頃のケア
幼少期から舌を動かす遊びや発音練習を取り入れることが効果的です。たとえば、口腔筋機能療法(MFT)や正しい舌の使い方を意識したトレーニングが予防にもつながります。
また、日頃から正しい姿勢や鼻呼吸を意識することも重要です。滑舌やいびきが気になる場合は、早めに専門機関へ相談しましょう。
さいごに
舌小帯短縮症は、早期発見と適切なケアで改善が見込める疾患です。滑舌やいびきなど、日常で感じる小さな違和感が大きなサインであることもあります。
気になる症状があれば、遠慮せず専門医にご相談ください。お子さまの健やかな発音と睡眠を守るために、私たち医療機関がお手伝いします。