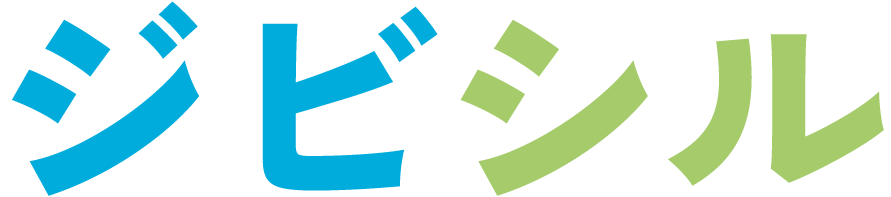「アッシャー症候群」と聞いても、ピンと来ない方も多いかもしれませんが、この病気は先天的に視力と聴力の両方に影響を与える遺伝性疾患です。「聞こえにくさ(感音性難聴)」と、成長してから現れる「見えにくさ(網膜色素変性症:夜盲・視野狭窄)」があり、日本では2020年時点で約200例が登録され、希少指定難病に登録されています。
早期に気づけば、補聴器や人工内耳、ビタミン療法などで症状の進行を抑え、QOL(生活の質)を高く保つことができます。特に小児の難聴や思春期以降の視力低下が気になる方には、知っておいてほしい病気です。
- 遺伝が関係する進行性の難病
- 日本人にも見られる難聴の原因
- 早期診断と対策が生活の質を左右
この疾患は早期の気づきが非常に重要です。特に家族歴や子どもの難聴に気づいた場合は、早めの検査・相談が大切です。
アッシャー症候群の主な症状

アッシャー症候群の主な症状は、先天性の感音性難聴と、思春期以降に進行する網膜色素変性症(夜盲・視野狭窄)です。
例えば、「小さい頃からテレビの音を大きくしないと聞こえない」「夜になると物が見えにくくなる」といったサインが見られます。
難聴の程度や進行速度はタイプによって異なるので、生まれてすぐには難聴がなくても、その後じわじわと進行していく場合があるので注意が必要です。重度〜中等度の聴力障害が見られることがあります。日本人においても2020年時点で204例が登録されており、注意が必要です。
アッシャー症候群の原因・なり易い方

アッシャー症候群は常染色体劣性遺伝によって起こる先天性疾患です。これは、両親のどちらもが保因者であった場合に発症の可能性があります。
タイプごとの原因遺伝子は以下の通りです。
- タイプ1:MYO7A, USH1C, CDH23, PCDH15, USH1G
- タイプ2:USH2A, ADGRV1, WHRN
- タイプ3:CLRN1, HARS
視覚障害の発症年齢は、タイプ1・2では10代以下、タイプ3は20歳以降が多いとされています。
検査/診断の方法
- 聴力検査(ABR):新生児期から可能で、音に対する脳波を見ることで評価します。
- 網膜電図(ERG):夜盲の症状が出る前でも診断可能な場合があります。
- 遺伝子検査:Usher症候群のタイプ分類や原因特定に重要です。
- タイプ1:MYO7A、CDH23など
- タイプ2:USH2A(全体の30%以上)
日本国内では2020年3月時点で204例が登録され、遺伝子検査は全体の56%に実施。
保険未収載のため検査率は限定的であり、今後の制度整備が望まれます。
アッシャー症候群の治療方法・回復期間の目安

現時点では疾患そのものを治療する方法は確立されていませんが、症状の軽減・進行抑制は可能です。
- 難聴には程度に応じて補聴器や人工内耳(特にUsher1型では早期の装用が推奨)
- 網膜色素変性にはビタミンA補充療法、遮光眼鏡の使用、視覚リハビリなどが行われます
- 遺伝子治療は研究段階であり、今後に期待が寄せられています
- MYO7AやCDH23変異に対する人工内耳の効果は高いと報告されています
- 将来的な視覚障害に備えた両側人工内耳の早期装用も重要な検討ポイントです
アッシャー症候群の類似症状
- 単独の網膜色素変性症
- 非遺伝性の感音性難聴
- 若年発症型両側性感音難聴
これらは似た症状を呈しますが、遺伝子検査での鑑別が重要です。

予防・日頃のケア
- 家族歴がある場合は出生前・出生後の遺伝子検査の検討
- 難聴と診断されたら、視力も定期チェック
- 夜盲・視野狭窄に備えて、明るい照明や補助器具を活用する生活環境の整備
さいごに
アッシャー症候群は聴覚と視覚の両方に関わる疾患ですが、早期に対応することで日常生活の支障を減らすことができます。とくに「家族歴」「乳幼児期の聴覚スクリーニング」「眼科検診」が重要で、疑わしい症状や家族歴がある場合は、専門医(耳鼻科・眼科・遺伝専門医)への相談をおすすめします。ご家族皆さまの安心につながることを願っております。
- 常染色体劣性遺伝:両親から同じ遺伝子変異を1つずつ受け取ると発症。
- ABR(聴性脳幹反応):頭に小さな電極を貼り、音に対する脳の反応を測定。
- ERG(網膜電図):網膜の電気的な働きを測り、どのくらい光に反応するかを調べる。
- QOL(Quality of Life):生活の質。医療では、日常生活の快適さや満足感を評価します。