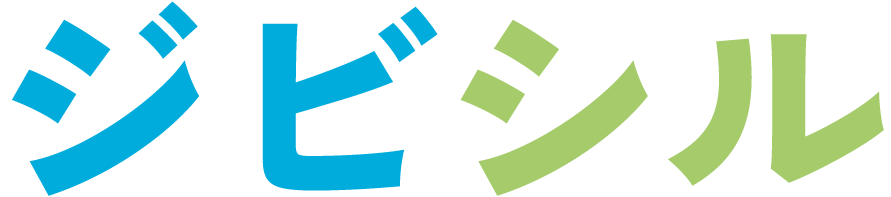朝起きたときに「口がカラカラ」「喉が痛い」と感じたことはありませんか?
もしかすると、それは“口呼吸”が原因かもしれません。
本来、私たちの体は鼻で呼吸するように設計されています。しかし、現代では慢性的な鼻づまりや生活習慣の影響で口呼吸をする人が増えています。特に子どもにおいては、その影響が顔や歯並びに影響を与えるなど、成長や健康に及ぶ可能性があるため、早期の対応が重要とされています
- 顔のゆがみの原因になることも
- 口臭やいびきの一因になる口呼吸
- 睡眠の質が下がる可能性も
睡眠中の口呼吸は、顔や歯並びに影響を与えるだけでなく、日常生活にも様々な悪影響を及ぼします。小児を中心とした調査では、風邪をひきやすい、唇が乾燥しやすいといった具体的な症状が多数報告されています。
口呼吸の主な症状
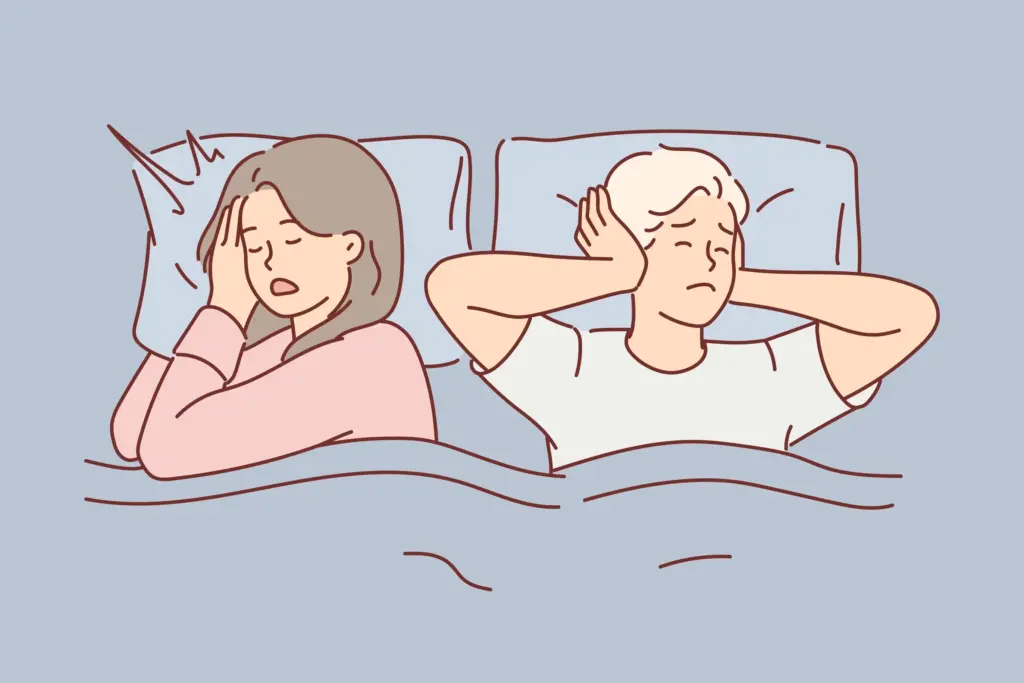
「朝起きたときに口が乾燥している」「人からいびきを指摘された」「なんとなく顔がむくみやすい」といった自覚がある方は注意が必要です。
また、日中の集中力の低下や口臭の悪化も、睡眠中の口呼吸によるものかもしれません。調査では、4〜6歳の小児のうち約22〜27%が口呼吸をしているとされ、風邪をひきやすい、唇の乾燥、聞き返しが多い、咀嚼や嚥下が苦手などの傾向が明らかになっています。
口呼吸の原因・口呼吸になりやすい人
口呼吸の主な原因は、鼻呼吸の妨げになる要因にあります。特に小児では、以下がリスク因子です。
- 上気道閉塞:アデノイド・扁桃腺の肥大、アレルギー性鼻炎(頻度が高い)
- 顔貌構造:上顎前突や狭い口蓋、唇閉鎖力の低下
- 睡眠中の障害:睡眠時無呼吸やいびきなどの合併
- 姿勢・筋力の問題:猫背や口周囲筋の弱さも影響
また、不十分な鼻呼吸が慢性化することで、習慣的な口呼吸が固定化される傾向があるため、早期発見が重要です。
口呼吸が及ぼす影響
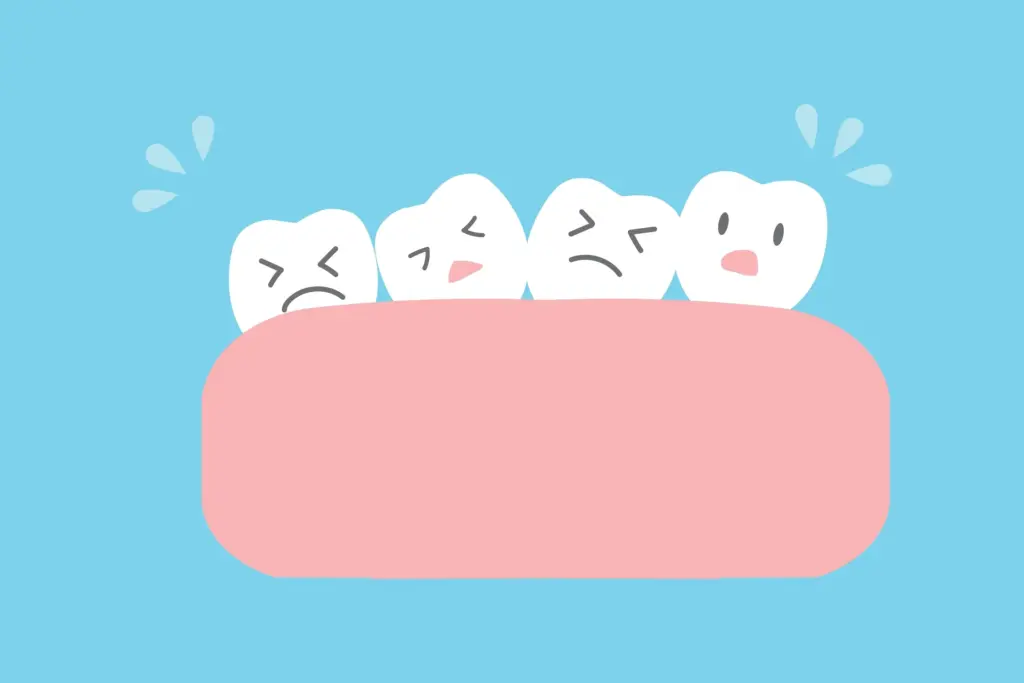
顎顔面・歯列の発達への影響
口呼吸は、顎顔面の異常発育や不正咬合(下顎後退・高口蓋・開咬など)と強く関連しています。
特に小児期に発症した場合、その影響は顔貌の骨格パターンや永久歯の歯並びにも及びます。
成長・全身の発育への影響
口呼吸は成長ホルモンの分泌低下と関連し、低身長や成長障害の要因にもなり得ます。
また、小児喘息との合併率も高いことが知られています。
口腔機能・顎関節機能の低下
- 唇閉鎖力・舌圧・咀嚼効率の低下
- 顎関節症(TMD)のリスク上昇
- 舌圧の低下
検査/診断の方法
耳鼻咽喉科では、まず問診により生活習慣や鼻閉の有無、いびきの頻度などを確認します。
その後、ファイバースコープ(内視鏡)で鼻腔や咽頭の状態を観察し、必要に応じて鼻腔通気度検査や睡眠検査(ポリソムノグラフィなど)を実施します。
また、小児では保護者からのアンケートを通じた評価も有効です。診察は痛みが少なく短時間で完了し、必要に応じて歯科や小児科と連携した対応も行われます。
治療の方法・回復期間の目安
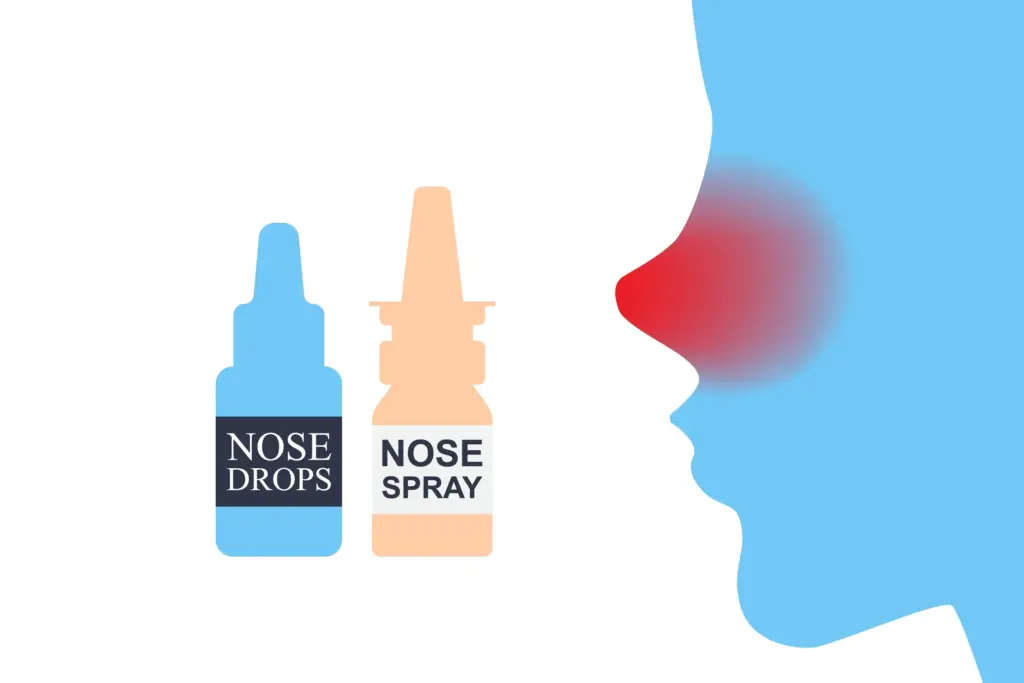
治療は原因に応じて行われます。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎には抗アレルギー薬やステロイド点鼻薬が使用され、1〜2週間で効果が見られるケースもあります。
口呼吸が習慣化している場合には、口周りの筋トレ(あいうべ体操)や、口閉じテープの活用が有効です。重度の場合は手術(鼻中隔矯正など)が必要なこともありますが、大半は保存的治療で改善します。
加えて、歯科矯正的アプローチ(顎の拡大装置やMFT:口腔筋機能療法)や、耳鼻咽喉科によるアデノイド・扁桃の評価と手術も検討される場合があります。とくに小児では、上顎の成長誘導や鼻腔通気の改善を目的とした介入が有効であるとされ、治療開始の適切なタイミングを見極めることが重要です。
これらを踏まえ、耳鼻科・歯科・小児科の多職種連携による包括的治療が推奨されます。
類似症状の疾患
睡眠時無呼吸症候群、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎などが類似の症状を引き起こします。いびき、口の乾燥、昼間の眠気などが共通し、自己判断は難しいため、専門医の診断を受けることが大切です。
口呼吸にならないための予防・日頃のケア
- 鼻呼吸を意識する習慣をつける
- 寝る前に鼻洗浄や部屋の加湿を行う
- デスクワークや作業時の姿勢を見直す
- あいうべ体操や口周囲の筋力トレーニングを日常的に行う
- アレルギー性鼻炎の早期治療を行う
これらのケアを日常的に実施することで、口呼吸の予防・改善につながります。
さいごに
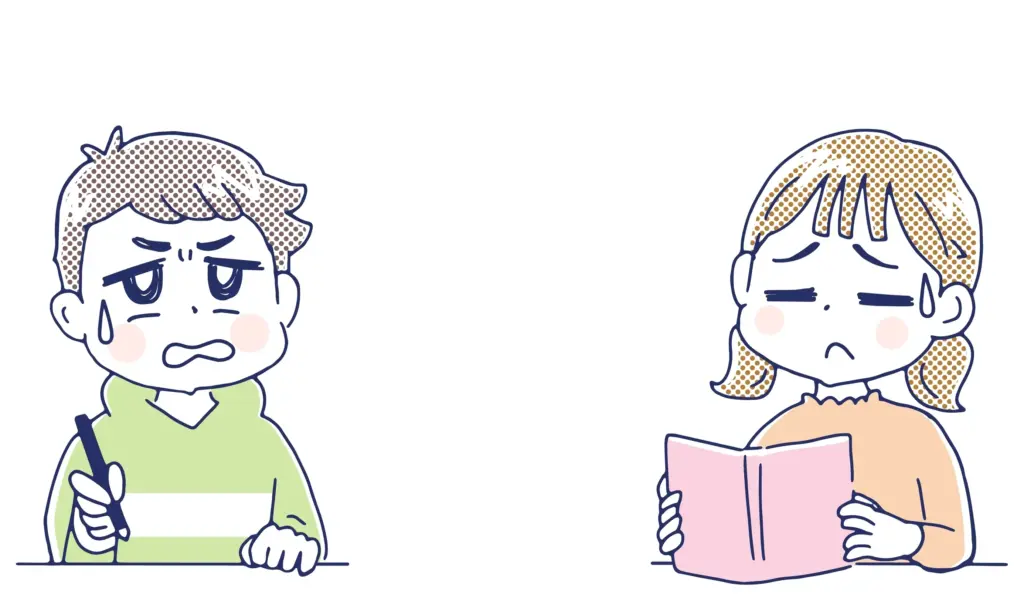
口呼吸は、単なる「癖」ではなく、顔面の成長、呼吸、嚥下、免疫、そして学業成績にまで影響を及ぼす全身的な問題です。
とくに小児期では成長発育への影響が大きく、早期発見・早期介入が、将来的なリスク軽減につながります。
耳鼻科・小児科と歯科(矯正歯科・小児歯科)の連携による包括的な対応が、子どもたちの健やかな成長を守るカギとなります。