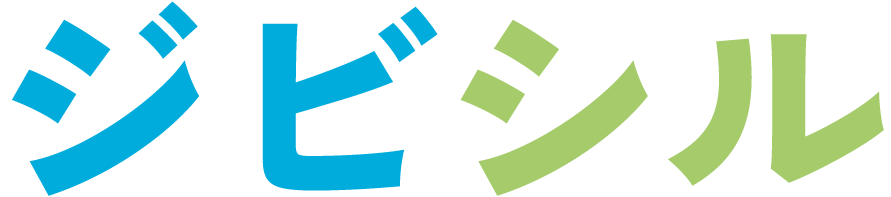夏になると体がだるくなったり、食欲が落ちたりする「夏バテ」。
実は、耳鼻科的な視点から見ても重要な症状が含まれているのをご存じですか?
耳・鼻・喉に関連した不調が「夏バテ」の原因や悪化要因になることもあります。
また、最新の研究では、熱ストレスによる腸管機能低下(leaky gut)や自律神経失調が夏バテと密接に関連していることが示唆されています。
- 吐き気やめまいは耳の不調や水分過多が原因のことも
- 症状が長引くなら漢方や生活改善で体質からケア
- 夏バテの治し方は内耳と腸の冷え対策がカギ
夏バテは全身の不調と関連しますが、耳鼻科的症状や胃腸・自律神経への影響も見逃せません。
夏バテの主な症状
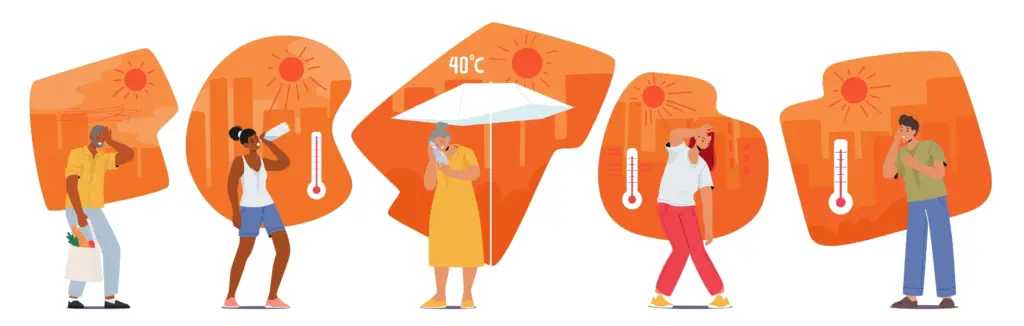
夏バテによって起こる症状は多岐にわたります。中でも耳鼻科で扱う症状としては以下のようなものがあります。
- 吐き気や食欲不振(自律神経の乱れや胃腸機能低下が関与)
- めまいや立ちくらみ(内耳の不調や水分バランス異常)
- のどの乾燥・痛み(冷房や脱水による粘膜のダメージ)
- 鼻詰まりや副鼻腔炎(冷風やウイルスによる悪化)
- 慢性的なだるさや集中力低下(夏の暑熱環境によるエネルギー低下)
特に高齢者では脱水や熱疲労との区別が難しく、早めの耳鼻科的対応が必要となります。
夏バテの原因・夏バテになり易い方

夏バテは、主に「自律神経の乱れ」「胃腸機能の低下」「水分・電解質のアンバランス」が要因です。
冷房と高温の温度差、冷たい飲料や食べ物の摂りすぎ、急な運動による腸への負担が複合して発症します。近年では「leaky gut(腸管透過性の異常)」が、腸からの炎症反応を誘発し、自律神経のバランスを崩す可能性があると指摘されています。
また、以下のような方は特に注意が必要です。
- 高齢者や子ども(体温調節が未熟)
- 冷房の効いた室内で長時間過ごす方
- 胃腸が弱い、ストレスが多い方
- 脱水状態、または水分を過剰摂取しがちな方
- 糖尿病・高血圧などの持病がある方
検査/診断の方法
耳鼻科では、以下のような検査で夏バテ関連症状を確認します。
- 聴力検査、平衡機能検査(めまいや耳閉感の原因を特定)
- 鼻や喉の内視鏡検査(咽喉ファイバーで炎症や乾燥の状態を確認)
- 血液検査(脱水の有無、炎症反応)
- 血圧・脈拍測定(自律神経の状態把握)
夏バテによる体調不良は、耳や喉の疾患との関連も見逃せません。検査はほとんどが15分〜30分程度で行え、明確な診断につながります。
夏バテの治療方法・回復期間の目安

治療の基本は「体のバランスを整えること」です。
症状に応じて以下の治療を行います。
- 内耳由来のめまい:抗めまい薬や利尿剤、ビタミンB群の補給
- 喉や鼻の不調:抗炎症薬、うがい、点鼻薬
- 自律神経の乱れ:漢方薬(補中益気湯、半夏厚朴湯など)
- 消化機能低下:整腸薬や水分・電解質の補給
生活改善では、十分な睡眠、朝食を含む栄養バランスの良い食事、冷たいものの摂りすぎ回避が重要です。
軽症であれば3〜5日程度、自律神経や胃腸への影響が強い場合は1〜2週間の経過をみます。
類似症状の疾患
夏バテと似た症状を示す疾患には、熱中症、自律神経失調症、急性胃腸炎、慢性副鼻腔炎、良性発作性頭位めまい症(BPPV)などがあります。
特に「吐き気」「だるさ」「のどの違和感」が重なる場合は、耳鼻科的チェックを推奨します。
予防・日頃のケア

以下の点に注意すると、夏バテを予防しやすくなります。
- 喉が渇いていなくてもこまめに水分補給(1.2〜1.5L/日)
- 果物(スイカやキウイ)や塩を含んだ食事で電解質も補給
- 朝食をしっかり食べ、代謝リズムを維持
- 過剰な冷房を避け、設定温度は28℃前後に
- 有酸素運動(ウォーキングなど)で暑熱順化を促進
- 鼻うがいや加湿でのどと鼻の粘膜を保湿
- 冷たい飲み物の一気飲みや極端な内部冷却は避ける
さいごに
夏バテは放っておくと慢性化したり、内耳や喉の炎症、自律神経失調症につながることもあります。
特に「吐き気」「頭痛」「のどの痛み」などが長引く場合は、耳鼻科での診察が役立ちます。
私たちは、体と心の両面から患者さんの夏の不調を支える存在でありたいと考えています。
どうぞお気軽にご相談ください。