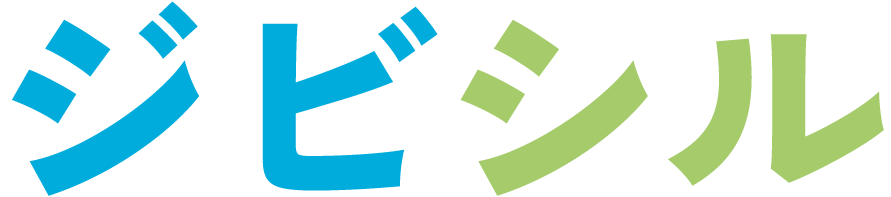「胸やけはないのに、のどの違和感や声のかすれが続くのはなぜ?」そんな疑問の背景には逆流性食道炎が隠れていることがあります。
耳鼻科での検査やファイバースコープが早期診断のカギになります。
- 耳鼻科でファイバースコープ検査が可能
- 胸やけがなくても逆流性食道炎の可能性あり
- 生活改善と薬で多くは数週間〜2か月で改善
耳鼻科で診断できる逆流性食道炎(咽喉頭逆流症を含む)について、症状・検査・治療を分かりやすく解説します。
逆流性食道炎の主な症状

- のどの違和感や異物感(何かが詰まった感じ)
- 乾いた咳や咳払いが長引く(2週間以上)
- 声のかすれ(嗄声)が続く、朝や会話で悪化
- のどのヒリヒリ感、慢性的なのどの痛み
- 食後や就寝時に症状が悪化
- 痰が絡む感じ、耳の違和感や耳の詰まり感
胸やけがなくても症状が現れる「サイレントリフラックス(咽喉頭逆流症:LPRD)」もあり、見逃されやすいのが特徴です。
逆流性食道炎の原因・なりやすい方
逆流性食道炎は、胃酸や消化液が食道からのど・声帯に及ぶことで炎症を引き起こします。
主な原因は、食道と胃の境目の筋肉(下部食道括約筋)のゆるみや、食後の横臥、肥満、加齢、腹圧上昇(前かがみ作業、きつい衣服)、喫煙、飲酒、脂っこい食事の摂取などです。ストレスや睡眠不足も悪化因子です。
また、声をよく使う方、長時間デスクワークをする方、妊娠中、鼻閉や睡眠時無呼吸症候群のある方は発症しやすい傾向があります。
小児では、夜間の咳や中耳炎を繰り返す背景に逆流が隠れていることもあります。
逆流性食道炎の検査/診断方法

耳鼻科ではまず問診とスコア(RSI:症状スコア、RFS:内視鏡所見スコア)を用いて評価します。そのうえでファイバースコープ(細い内視鏡)を鼻から挿入し、喉頭・下咽頭の炎症や浮腫、肉芽を観察します。検査時間は5〜10分程度で、当日に結果を確認可能です。
必要に応じて、胃カメラで食道炎や食道がん、好酸球性食道炎などを除外します。胸やけがなく胃カメラで異常がない場合は、24時間pHモニタリングやインピーダンス検査を行い、逆流の頻度・高さを測定することもあります。
診断は耳鼻科でのファイバースコープ所見、問診票、薬の効果を総合して行います。
逆流性食道炎の治療方法・回復期間の目安
治療の基本は生活習慣の改善と薬物療法です。
- 食後2〜3時間は横にならない、就寝時は上半身を10〜15cm高くする
- 脂っこい食事、辛い料理、チョコやコーヒー、炭酸飲料、アルコールは控える
- 体重管理(体重を5%以上減らすと改善しやすい)
- 禁煙、腹部を締め付ける服装を避ける
薬物療法ではPPIやP-CABを用い、2〜4週間で改善が見られることが多く、8週間程度で炎症も治まります。声のかすれが強い場合は8〜12週間かかることもあります。
再発例は投与の工夫や長期管理が必要です。
難治例は、耳鼻科・消化器内科・外科が連携し、追加検査や外科的治療を検討します。
類似症状の疾患
慢性上咽頭炎、咽喉頭異常感症、声帯ポリープ・結節、アレルギー性副鼻腔炎や後鼻漏、気管支ぜんそく、ACE阻害薬による咳、副鼻腔炎、喉頭がん、食道がんなどが類似症状を示します。
内視鏡所見や追加検査での鑑別が重要です。
逆流性食道炎にならないための予防・日頃のケア
- 夕食は就寝3時間前まで、腹八分目を意識
- 枕やベッドを10〜15cm高くする
- 脂っこい料理・柑橘・チョコ・炭酸・アルコールを控える
- 前かがみ作業や腹部圧迫を避ける
- 体重をBMI25未満に維持
- 会食や飲酒後は制酸薬の頓用を検討
- 室内加湿や声の酷使を避ける
さいごに

耳鼻科では逆流性食道炎を、ファイバースコープ検査と適切な診断手法で見極められます。多くは生活改善と薬で改善可能ですが、難治例もあります。
その場合も消化器内科や外科と連携し、確実な解決策を探ります。のどの違和感や咳が続く方は、早めに耳鼻科を受診し安心してください。