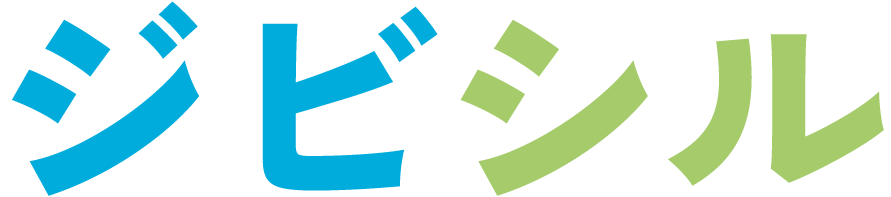「慢性的なだるさや不眠、めまいが続くのは自律神経の乱れ?」と感じていませんか。
実は鼻の奥(上咽頭)の慢性炎症が関わることがあります。
近年の研究では、耳鼻科で行う上咽頭擦過療法(EAT)が自律神経機能に影響を与えることも報告されています。
耳鼻科で原因を確かめ、適切に対処することで改善の糸口が見つかります。
- 自律神経の乱れと関連しうる炎症
- 治し方は耳鼻科+生活改善が軸
- 漢方や市販薬は補助的な選択肢
上咽頭の炎症は見逃されやすく、症状が多彩です。
まず耳鼻科で状態を確認し、「治らない」と感じる前に原因を整理しましょう。
EATや生活習慣改善、漢方を含む多面的治療で回復を目指します。
慢性上咽頭炎の主な症状
- 鼻の奥や喉の違和感・ヒリヒリ感が続く。
- 後鼻漏(鼻水が喉に落ちる)で、咳払いが1日10回以上。
- 乾いた咳や痰、鼻声、声がれが続く。
- 頭痛や目の奥の痛み、首・肩こり、耳閉感や耳鳴り。
- 全身倦怠感、だるさ、微熱(37.0〜37.4℃程度)が続く。
- 寝つきが悪い・途中で目が覚める、朝の倦怠感。
- めまい、動悸、胃のむかつき・食欲低下など自律神経症状。
これらは個々に出たり、季節や疲労・ストレスで悪化しやすいのが特徴です。
慢性上咽頭炎の原因・慢性上咽頭炎になり易い方
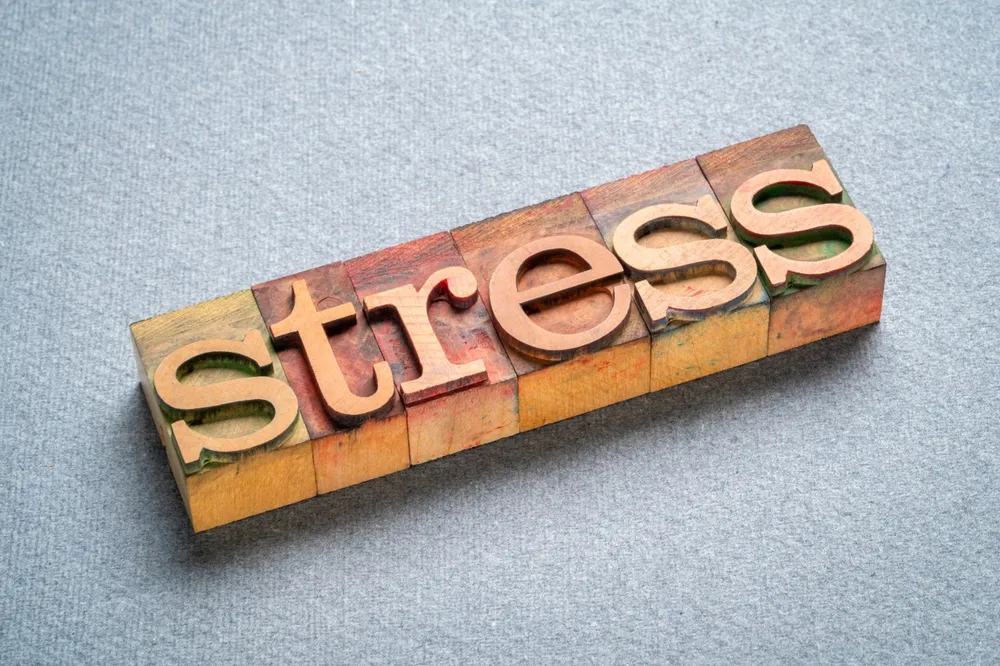
上咽頭は鼻と喉の境目で、ウイルス・細菌の刺激、アレルギー、乾燥や粉じん、胃食道逆流(逆流性咽喉頭炎)などで慢性的に炎症を起こします。
炎症部には自律神経(特に迷走神経)関連の神経終末が多く、持続刺激が「自律神経の乱れ」を助長します。
発症・遷延しやすいのは、花粉症や鼻炎持ち、鼻うがいが不適切な方、口呼吸・いびき、長時間のデスクワークや睡眠不足、ストレス過多、空気の乾燥する季節(秋冬)や冷えやすい方、胃酸逆流のある方です。
感冒後に症状が取れず「治らない」と感じるケースも多く、生活環境と体調の両面が関与します。
慢性上咽頭炎の検査/診断方法
耳鼻科での内視鏡(咽喉ファイバー)検査が基本です。
所要は約1〜3分で、上咽頭の発赤・腫脹・粘液付着を観察します。
慢性化すると見た目が軽くても症状が強いことがあり、診断補助として綿棒で上咽頭を軽く擦過(Bスポット/EAT)し、痛みや点状出血の有無を確認します。
これは「診断的治療」として位置づけられ、反応の強さが炎症の目安になります。
最近の研究では、EATが交感神経と副交感神経を交互に刺激しつつ、経時的に副交感神経活動を抑制し、血圧変動を安定させる作用があると示されました。必要に応じて、
- 咽頭・鼻咽頭培養や好酸球評価(アレルギー素因)
- 胃食道逆流が疑わしい場合の消化器評価
- 甲状腺機能・貧血等の血液検査(鑑別)
を行います。検査は外来で完了し、その場でおおよその見立てが可能です。
慢性上咽頭炎の治療方法・回復期間の目安

耳鼻科での局所治療
上咽頭擦過療法(Bスポット/EAT):週1回を目安にまず4〜10回。
痛みはあるものの、進むほど反応が軽くなる傾向。EATの臨床研究では、症状改善率が約68〜80%と報告され、自律神経のバランス改善や血圧安定に寄与する可能性があります。
併用として吸入(ネブライザー)、点鼻ステロイドや抗炎症薬を用います。
生活改善(治し方の土台)
鼻呼吸化、胃酸逆流予防(就寝前2〜3時間は飲食を避ける)、湿度40〜60%維持、十分な睡眠・ストレス緩和、首回り保温。
市販薬・セルフケア
トローチ(殺菌・消炎)、うがい薬は補助。生理食塩水の鼻洗浄は“やり過ぎない・正しい姿勢”で。アルコールや辛味刺激は悪化要因。
漢方
体質に応じて麦門冬湯、小柴胡湯、半夏厚朴湯、葛根湯などを選択。専門医判断で処方。
回復目安
軽症:2〜4週間で日常の不快感が半減。中等症:4〜12週間で波はあるが改善傾向。難治例は3〜6か月以上の継続が必要なこともあります。
類似症状の疾患
咽喉頭異常感症、胃食道逆流症(LPR)、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、緊張型頭痛、起立性調節障害、甲状腺機能異常、うつ・不安障害、慢性疲労症候群など。
まず耳鼻科で器質疾患を除外し、必要に応じて内科・心療内科と連携します。
慢性上咽頭炎にならないための予防・日頃のケア
- 室内湿度40〜60%を維持。
- 就寝2〜3時間前の飲食・飲酒を控える。
- マスク・スヌードで上咽頭の乾燥と冷えを防ぐ。
- 温かい蒸気吸入を毎日1回以上取り入れる。
- 正しい鼻洗浄(等張・ぬるま湯、前傾姿勢で)。
- 花粉・粉じん環境では帰宅後すぐ洗顔・鼻洗い・うがい。
- 口呼吸是正(鼻づまり治療、就寝時の口閉じテープ)。
さいごに
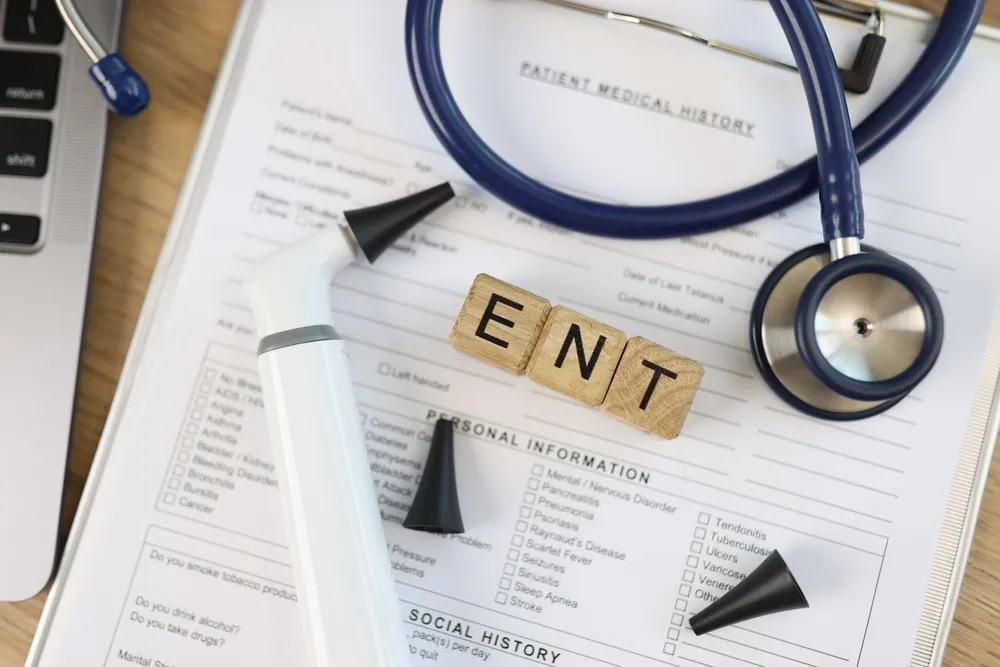
耳鼻咽喉科医の立場から、慢性上咽頭炎は「自律神経の乱れ」を助長しうる見過ごされやすい炎症です。
最新研究でも、耳鼻科での上咽頭擦過療法が自律神経反射や血圧調整を改善しうる可能性が示されています。
見た目の所見が乏しくても、丁寧な診察と局所治療、生活整備、必要に応じた漢方を組み合わせることで多くの方が改善します。
長引く不調で「治らない」と感じたら、一度耳鼻科で上咽頭を確認しましょう。早期介入が回復への近道です。