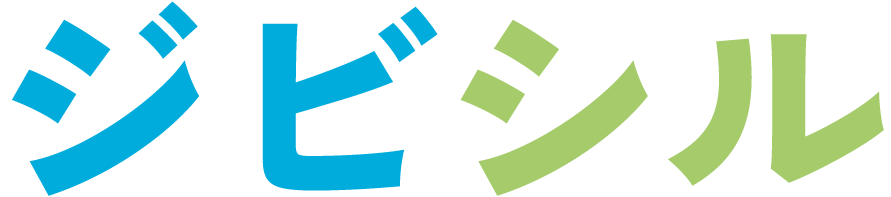「聴覚検査って何をするの?」「聞こえにくいと感じたら何科に行けばいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
とくに新生児の聴覚検査や低音が聞こえないといった症状がある場合は、早めの対処が大切です。
- 聴覚検査は見方を知ることで理解しやすい
- アプリでも簡単にセルフチェック可能
- 新生児も生後すぐにスクリーニング検査
正確な検査を受けることで早期発見・早期治療が可能になります。
次に具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
聴覚異常の主な症状
- 人の声が聞き取りにくい
- 低音だけが聞こえにくい(電話の声や車のエンジン音など)
- 呼びかけに反応しない(特に新生児の場合)
- 聞き返しが多い
- TVや音楽の音量が大きくなる
「低音が聞こえない」と感じたときには、特定の聴覚障害の可能性があります。
症状が進行すると、日常生活に支障をきたすこともありますので、注意が必要です。
聴覚異常の原因

聴覚異常の原因には、加齢、騒音、ウイルス感染、遺伝、ストレスなどさまざまです。
特に低音域が聞こえにくい場合は、突発性難聴やメニエール病などが疑われます。
また、新生児の聴覚障害は先天的要因も多く、スクリーニング検査が義務化されている地域もあります。
騒音下での作業や長時間のイヤホン使用も難聴のリスク因子となります。
検査/診断の方法
耳鼻科では複数の聴覚検査を組み合わせて診断を行います。以下に主な検査を紹介します。
- 純音聴力検査:最も基本的な検査で、周波数ごとの聴力を測定します。結果はオージオグラムとして表示され、その見方を理解することで聴力の状態が把握できます。低音域・高音域のどちらに障害があるかを評価可能です。
- 語音聴力検査:言葉の聞き取り能力を調べる検査で、語音了解閾値と語音弁別能を測定します。日常会話の聞き取りや補聴器適応の判定に重要です。
- 耳音響放射(OAE)検査:外有毛細胞の機能を調べる他覚的検査。特に新生児スクリーニングに使用され、軽度の内耳障害でも検出可能です。ただし、伝音難聴があると反応が得られないため注意が必要です。
- 聴性脳幹反応(ABR)検査:脳幹までの聴覚経路を評価する検査で、新生児や意識のない方にも実施可能です。特に後迷路性難聴や聴神経腫瘍の診断に有効です。クリック音ABRでは高音域を反映しやすく、低音の評価はASSR(聴性定常反応)が適しています。
- ティンパノメトリー:鼓膜と中耳の動きを評価し、中耳炎の診断に有効です。鼓膜の動きの見方から滲出性中耳炎や耳小骨異常を検出できます。
- 音響性耳小骨筋反射(AR):強い音に対する反射反応を見る検査で、内耳〜脳幹までの経路評価や顔面神経麻痺、機能性難聴の補助診断に使われます。
- 乳幼児専用の聴力検査:BOA(聴性行動反応検査)、COR(条件詮索反応)、ピープショウ、遊戯聴力検査など、年齢ごとに適した検査方法が用意されています。
また、近年では家庭で使用できる聴力チェックアプリも普及しており、簡易的な自己判断に活用できます。
疾患ごとの聴覚障害治療の方法・回復期間の目安

原因に応じて治療は異なります。
- 突発性難聴:ステロイド治療を早期に開始(発症から7日以内)することで、改善率が高くなります。
- 中耳炎:抗生剤や鼓膜切開で治療。1〜2週間で改善することが多いです。
- メニエール病:生活指導、利尿剤、めまい治療が中心。
- 補聴器・人工内耳:感音難聴や高齢者の聴力低下には補聴器が有効。語音弁別能が著しく悪い場合は人工内耳も検討されます。
早期発見がカギとなり、治療開始のタイミングが回復期間に大きく影響します。
その他、聴覚に影響のある疾患
低音が聞こえにくいという症状は、突発性難聴、メニエール病、耳垢塞栓、耳管狭窄、または聴神経腫瘍でも見られます。
どの疾患かを見極めるには、専門的な検査が必要です。
予防・日頃のケア
- 長時間のイヤホンや大音量での音楽視聴を避ける
- 騒音環境での作業には耳栓などで保護を
- 定期的な耳鼻科受診で聴力の変化を確認
- 新生児は出産直後に聴覚スクリーニングを受けることが重要
- 聴力の変化に気づいたら早めに耳鼻科を受診
- スマホ用のアプリで定期的なセルフチェックを行うのも有効です
さいごに

聴覚は私たちの社会生活や学習、仕事に大きく関わる大切な感覚です。
特に「低音が聞こえない」「話が聞き取りにくい」といった症状がある場合、早期の検査が重要です。
聴覚検査の見方を知ることで、ご自身やお子さまの健康管理に役立ちます。
不安を感じたら、迷わず耳鼻科にご相談ください。