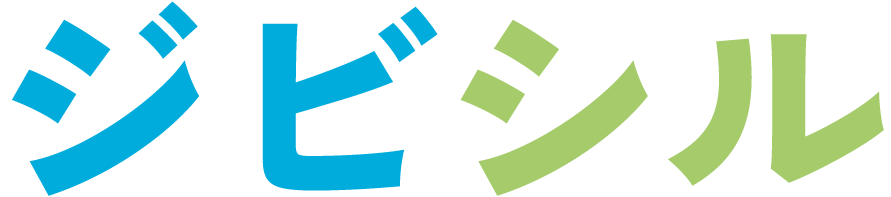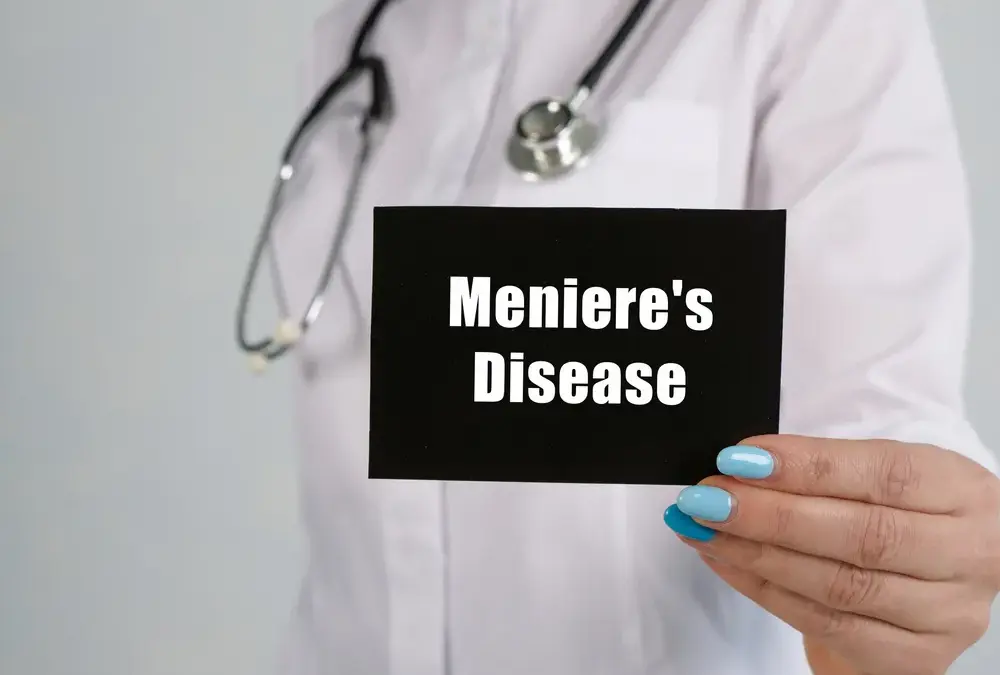メニエール病は、めまいや耳鳴り、難聴を引き起こす病気で、日常生活に大きな影響を与えることがあります。また、類似した症状を示す遅発性内リンパ水腫は2015年に厚生労働省の難病指定を受けており、どちらも早期の発見と適切な治療が重要です。初期症状を見逃さず、正しい知識を身につけましょう。
- メニエール病は初期症状の段階で対策が重要
- 遅発性内リンパ水腫は厚生労働省が難病指定している疾患
- 性行為の影響は?性行為をしても大丈夫?
- ストレスや生活習慣の改善が予防に有効
メニエール病の主な症状

メニエール病・遅発性内リンパ水腫の主な症状は、回転性のめまい、耳鳴り、難聴、耳の閉塞感などです。特にめまいは突然起こり、数十分から数時間続くことがあります。発作時には吐き気や嘔吐を伴うこともあります。初期症状としては、耳が詰まった感じや軽い耳鳴りが現れることが多く、放置すると症状が悪化する可能性があります。また、性行為によるメニエール病への影響は、血圧変動や自律神経の活性化を伴い症状が悪化するケースもありますが、症状が軽度など多くの場合では特に制限はありません。
メニエール病は、めまい発作と聴覚症状が同時または交互に現れることが特徴で、遅発性内リンパ水腫は高度感音難聴が先行し、その後数年から数十年の経過を経てめまい発作が発症する疾患です。
遅発性内リンパ水腫との違い
| 項目 | メニエール病 | 遅発性内リンパ水腫 |
|---|---|---|
| 発症パターン | 繰り返すめまい発作、聴力変動 | 高度感音難聴が先行し、数年~数十年後にめまい発作が出現 |
| 聴力 | 変動しながら進行性に低下 | すでに高度難聴があるため、難聴の進行はしない |
| 片側・両側 | 90%は片側発症、10%は両側発症 | 同側型と対側型がある |
| 疫学 | 10万人あたり35~48人 | 日本で患者数4,000~5,000人 |
| 主な誘因 | ストレス、睡眠不足、過労、気圧変化 | 先行する高度感音難聴(原因不明が多い) |
| 進行リスク | 慢性化すると持続性の難聴に | 対側型ではもう片耳も発症するリスク |
メニエール病の原因・メニエール病になりやすい方

メニエール病・遅発性内リンパ水腫の原因は、内耳にあるリンパ液の異常な増加とされています。ストレスや睡眠不足、不規則な生活習慣が発症のリスクを高める要因となります。また、30~50代の方に多く見られ、特に女性に発症しやすい傾向があります。特にストレスとの関係は示唆されており、精神的なプレッシャーや疲労が蓄積されている場合に発症しやすいといわれております。
メニエール病の検査・診断の方法
メニエール病・遅発性内リンパ水腫の診断にはそれぞれの診断基準があり、問診と聴力検査、平衡機能検査が行われます。聴力検査では、特に低音域の難聴が見られることが多く、繰り返し検査をすることで診断が確定します。また、MRIやCTスキャンを用いて他の疾患との鑑別診断を行う場合もあります。
メニエール病の治療方法・回復期間の目安
メニエール病の治療には、薬物療法や生活習慣の改善が中心となります。薬物療法では、めまいを抑える抗めまい薬やステロイド、内耳のリンパ液を調整する利尿剤が使用されます。症状が重い場合には、手術が検討されることもあります。発作の頻度や程度により個人差はありますが、適切な治療を続けることで症状のコントロールが可能です。
メニエール病の類似症状の疾患
突発性難聴、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎などが類似の症状を伴います。
メニエール病にならないための予防・日頃のケア

- ストレスを溜めないようにする(リラックス方法を取り入れる)
- 規則正しい生活を心がける(睡眠をしっかりとる)
- 塩分を控えた食事を意識する(内耳のリンパ液の異常を防ぐ)
- 適度な運動で血行を促進する
さいごに
メニエール病や遅発性内リンパ水腫はめまいや難聴の症状を特徴としており、遅発性内リンパ水腫は難病指定されている疾患ですが、適切な治療と生活習慣の見直しで症状のコントロールが可能です。初期症状を見逃さず、早めに医療機関を受診することが大切です。日々の生活習慣を見直し、健康を維持することを心がけましょう。
参考文献:メニエール病・遅発性水腫診療ガイドライン2020年版