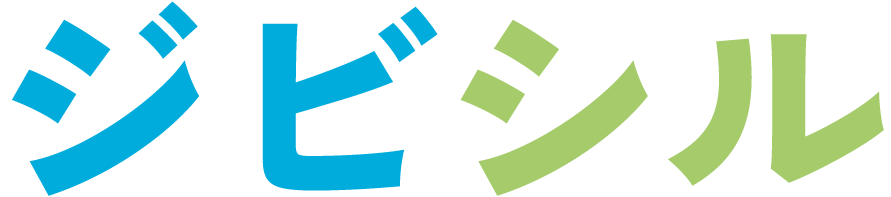起立性調節障害(OD)は、朝起きられない、立ちくらみ、倦怠感などの症状が特徴的な疾患で、特に中学生に多く見られます。親として「何科を受診すればよいのか?」「子どもへの接し方はどうすればいいのか?」と悩む方も多いでしょう。本記事では、起立性調節障害の症状や診断方法、親の対応について解説します。
- 起立性調節障害は中学生に多く見られる
- 診療科は小児科または内科、場合によっては心療内科
- 母親の理解とサポートが回復のカギ
起立性調節障害の主な症状

起立性調節障害の主な症状には、以下のようなものがあります。
- 朝起きられず、午前中に強い倦怠感がある
- 立ち上がるとめまいや動悸がする
- 頭痛や吐き気を伴うことがある
- 集中力が続かず、授業中に眠くなる
- 午後からは少し元気になる
このような症状が続く場合、早めの受診を検討しましょう。
受診をする際には何科が良いのかというもの悩まれている人も多いと思いますが、小児科や内科(循環器科・神経内科)の受診が一般的です。
起立性調節障害の原因・起立性調節障害になりやすい方

起立性調節障害は、自律神経のバランスが乱れることによって起こります。特に、成長期の子どもはホルモンバランスの変化もあり、発症しやすい傾向があります。中学生に多いのは、身長の急激な成長や生活リズムの乱れが関係していると考えられています。また、ストレスが引き金となることもあり、性格が几帳面で責任感の強い子どもがかかりやすいとも言われています。過干渉や勉強へのプレッシャーなど、両親特に母親の性格との関係性について示唆される記事も見受けられますが、この関連性については明確にはなっておらず、思春期のホルモン変化や環境要因(学校や対人関係が変わる)の影響がより強いものと考えられています。
起立性調節障害の検査・診断の方法
自律神経のバランスが崩れ、血圧や心拍数の調節がうまくいかなくなる疾患のため、起立性調節障害の診断には、問診や身体検査が中心となります。
- 直立試験(10分間の立位で血圧や心拍の変化を測定)
- 血液検査(貧血や他の疾患との鑑別)
- 心電図検査(不整脈の有無を確認)
これらの検査をもとに、起立性調節障害と診断されることが多いです。
起立性調節障害の治療方法・回復期間の目安
治療の基本は、生活習慣の改善です。
- 朝起きる時間を一定にする
- 水分と塩分をしっかり摂る
- 適度な運動を行い、血流を促す
- ストレスをためないようリラックスできる環境を作る
起立性調節障害の類似症状の疾患

耳鼻科の疾患(メニエール病、良性発作性頭位めまい症など)、自律神経失調症などが類似の症状を示すことがあります。
そのため、耳鼻科系の疾患と区別するために、耳鼻科の受診をきっかけに起立性調整障害に気付くケースも多々あります。
起立性調節障害にならないための予防・日頃のケア
- 朝食をしっかり摂る(血圧の安定に役立つ)
- 適度な運動で血流を良くする
- ストレスを軽減し、規則正しい生活を心がける
- 親が子どもを責めず、理解し寄り添うことが大切
さいごに
起立性調節障害は中学生に多く見られ、適切な対応と理解が重要です。親としては、症状を「怠け」と誤解せず、温かく見守る姿勢が求められます。受診すべき診療科は、小児科や内科ですが、ストレスが原因の場合は心療内科の相談も検討しましょう。子どもと共に、焦らず向き合っていくことが回復への第一歩です。