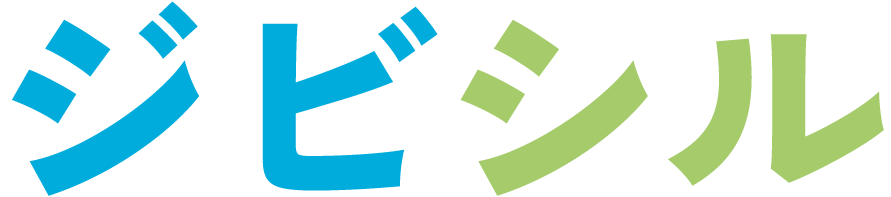「食事の味がしない」「何を食べても苦い」——そんな味覚障害を経験したことはありませんか?近年では、新型コロナウイルスやインフルエンザにかかった後に味覚が変化するケースが増えています。味覚障害の原因や対策について詳しく解説します。
POINT
- 味覚障害はコロナやインフルエンザ後に発症することがある
- 嗅覚障害と同時に発症することがある
- 早めの診断と適切な治療が回復の鍵となる
- 漢方を含む治療法で改善が期待できる
味覚障害の主な症状
味覚障害の症状はさまざまですが、多くの方が以下のような異変を感じます。
- 味がしない・薄く感じる(味覚減退)
- 何を食べても苦い、または金属のような味がする(異味症)
- 特定の味だけがわからない(部分的味覚障害)
- 口の中が常に甘い・苦い・しょっぱいと感じる(持続性の味覚異常)
これらの症状は風邪やウイルス感染後に現れることが多く、数週間で自然に回復することもあれば、長期間続くこともあります。
味覚障害の原因・味覚障害になり易い方

味覚障害の原因はさまざまですが、特に近年増えているのがコロナウイルス感染後やインフルエンザ後の後遺症です。以下のような要因が影響します。
- 亜鉛不足(味蕾の働きが低下)
- 加齢による味覚低下(50代以降に増加)
- ストレスや自律神経の乱れ(交感神経が優位になると味覚が鈍くなる)
- 薬の副作用(抗生物質や降圧剤など)
- ウイルスや真菌(カビ)による舌炎
味覚障害の検査・診断の方法
味覚障害の診断には、以下のような検査が行われます。
- 味覚検査:甘味・塩味・酸味・苦味の感度を確認
- 視触診・咽喉ファイバー:舌や口腔内に異常がないかチェック
- 血液検査:亜鉛・鉄・ビタミン不足やその他の異常を調べる
障害の程度や原因を正しく検査し、早期診断することが回復の近道となります。
味覚障害の治療方法・回復期間の目安
味覚障害の治療には、原因に応じた方法が取られます。
- 亜鉛補充:亜鉛不足が原因の場合、亜鉛剤の処方や、サプリメントや食品(牡蠣、レバーなど)で補います。
- 漢方薬の使用:主なものとして以下の漢方があります。
- 「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」:免疫力を高め、味覚回復を促す
- 「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」:胃腸の不調を整え、味覚改善に効果的
- 神経の調整:ストレスや自律神経の乱れが原因の場合、リラックスする生活習慣が重要
回復期間は数週間〜数ヶ月程度ですが、早めに治療を始めることで改善しやすくなります。
味覚障害を引き起こす他の疾患
- 嗅覚障害(においがしない、においを誤認する)
- ドライマウス(口の乾燥が原因で味を感じにくくなる)
味覚障害にならないための予防・日頃のケア

味覚障害を防ぐためには、以下のポイントを意識しましょう。
- バランスの取れた食事を心がける(特に亜鉛を意識)
- 適度な運動と睡眠で自律神経を整える
- 感染症予防(マスク・手洗い・ワクチン接種)を徹底する
- 漢方やサプリメントを活用し、健康管理をする
さいごに
味覚障害は一時的なものが多いですが、2週間以上続く場合は適切な診断と治療が重要です。特にコロナやインフルエンザ後の味覚異常は、放置せずに早めに耳鼻科を受診しましょう。漢方を取り入れることで、体質改善をしながら回復を促すことも可能です。味覚が戻るまでの間も、栄養バランスの良い食事を意識し、日常生活を整えることが大切です。