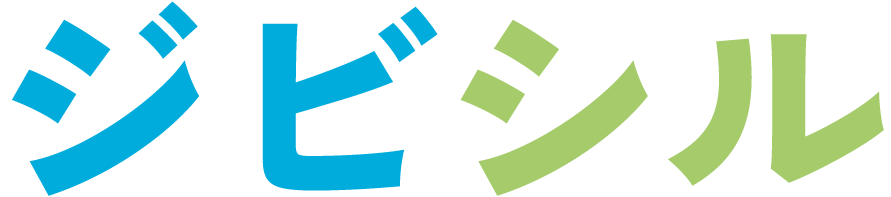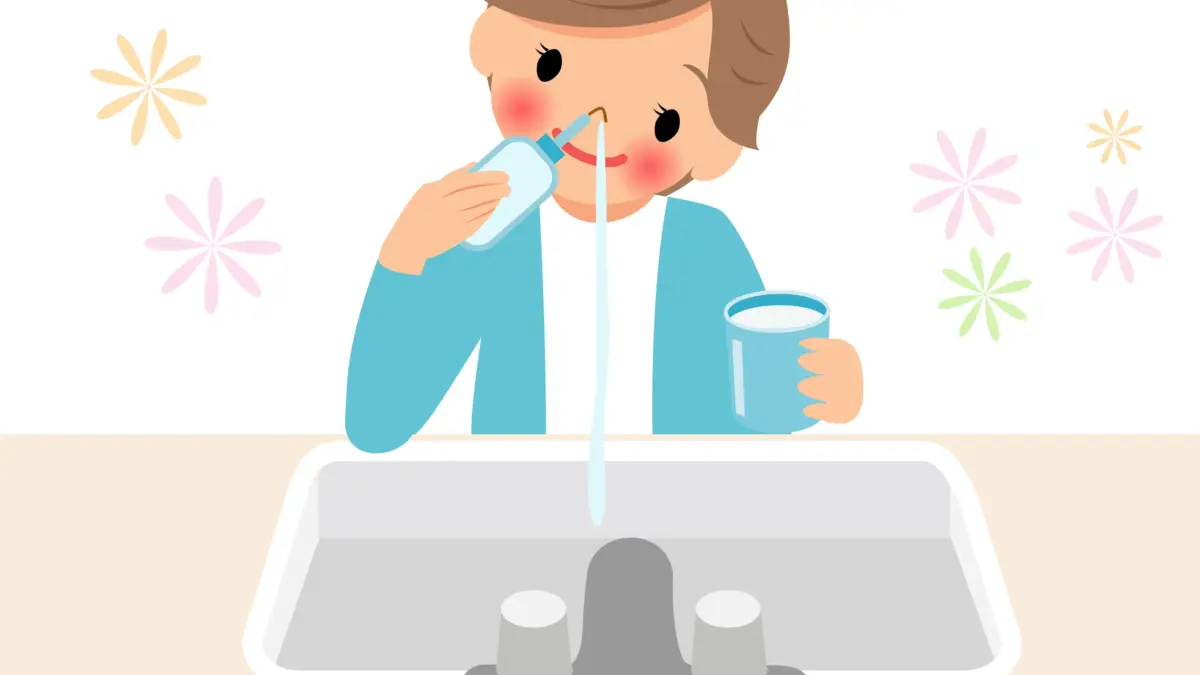「鼻うがいって本当に効果があるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
市販の製品や水道水を使った鼻うがいが、どのような効果をもたらすのか、そして副鼻腔炎や蓄膿症にどう影響するのかを、最新のエビデンスをもとに解説します。
- 吐き気やめまいは耳の不調や水分過多が原因のことも
- 症状が長引くなら漢方や生活改善で体質からケア
- 夏バテの治し方は内耳と腸の冷え対策がカギ
正しく行えばすごい効果を発揮する鼻うがい。
手軽にできるセルフケアとして注目されています。
この記事では、科学的根拠に基づきながら、鼻うがいのメリットと注意点について解説していきます。
鼻うがいが効果的とされる代表的な症状
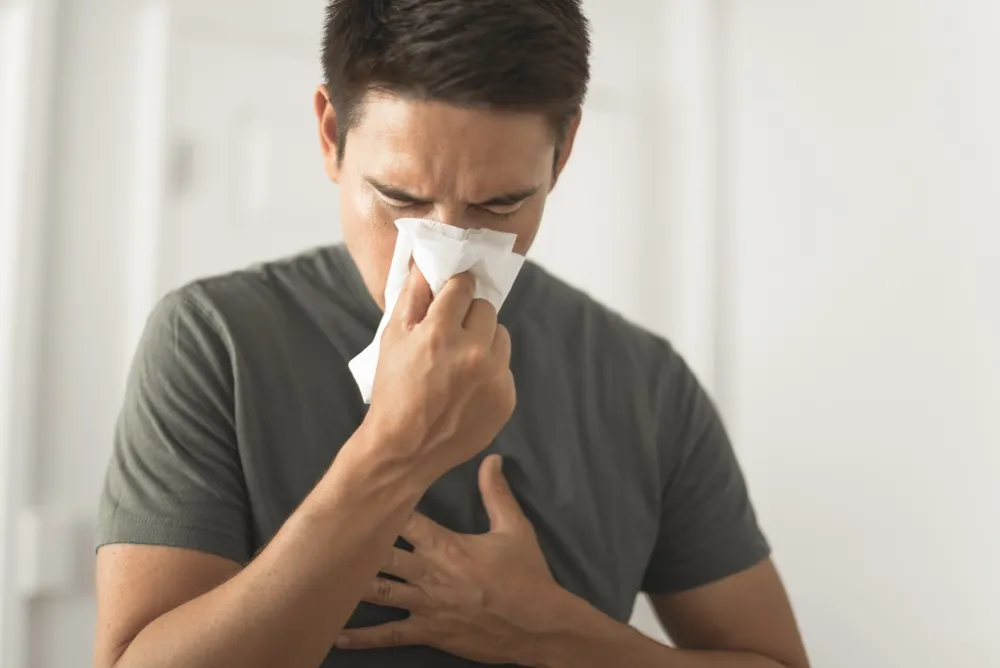
鼻うがいが効果的とされる代表的な症状には、以下のようなものがあります。
- 鼻づまりが続いて呼吸がしにくい
- 粘り気のある鼻水が出る(黄色や緑色)
- 後鼻漏により咳や喉の違和感が続く
- 匂いがしづらい・味が分かりにくい
- 顔や頭の奥が重い、頭痛がある
これらは副鼻腔炎や慢性鼻炎、アレルギー性鼻炎、風邪による鼻症状であることが多く、鼻うがいによって症状緩和が期待できます。
鼻うがいが必要な人・背景
副鼻腔炎や蓄膿症では、副鼻腔内に粘液がたまり、感染や炎症を繰り返します。
鼻腔粘膜の線毛運動が低下することで、炎症性メディエーターや病原菌が排出されにくくなり、慢性化につながります。
鼻うがいは、こうした異物を物理的に洗い流すことで、症状の改善・再発予防に役立ちます。
特に、以下の方に推奨されます。
- 慢性副鼻腔炎や蓄膿症の方
- アレルギー性鼻炎をお持ちの方
- 鼻づまりで睡眠に支障がある方
- 花粉症やハウスダストに敏感な方
- 上咽頭炎、後鼻漏が気になる方
COVID-19後遺症(Long COVID)でも、慢性上咽頭炎の合併が報告されており、鼻うがいの意義が高まっています。
鼻うがいの方法と市販製品の活用法

鼻うがいは、専用の洗浄器やミストスプレー、市販のパウダー入りの生理食塩水セットを使うことで、安全かつ効果的に行えます。
鼻うがいの基本手順
- 洗浄液を用意(市販の粉+ぬるま湯 or 自作の0.9%食塩水)
- 鼻から液を流し入れ、反対側の鼻または口から排出
- 両側交互に行う(1日1~2回)
- 使用後は洗浄器を清潔に保つ
※水道水はそのまま使用せず、必ず煮沸または精製水を使用してください。
おすすめ市販品
特にミストスプレー型は、刺激が少なく小児でも使いやすいとされ、安全性も高いと報告されています。
鼻うがいの効果とその理由
鼻うがいによって得られる主な効果は次のとおりです。
- 鼻づまりの緩和、通気性の改善
- 粘液や細菌、ウイルス、アレルゲンの除去
- 線毛運動の正常化、粘膜の機能回復
- 後鼻漏の軽減、喉への刺激予防
- 鼻腔内の炎症軽減と再発予防
研究では、鼻うがいを2週間継続した群では、鼻腔開存面積の有意な増加、細菌の陰性化、症状スコアの改善が報告されています。
また、EAT(上咽頭擦過療法)と併用することで、慢性上咽頭炎の自覚症状(後鼻漏、咳、頭痛など)の改善率が高まるとされています【18†32_33.pdf†L1-L20】。
鼻うがいの注意点

1. 必ず清潔な食塩水を使うこと
- 水道水をそのまま使うのはNGです。必ず煮沸した水や精製水に適正濃度(0.9%)の食塩を加えた食塩水を使用しましょう。
- 冷たすぎず、体温に近い温度(約37℃)に調整してください。
2. 無理に強く流さない・鼻を強くかまない
- 強く洗浄液を吸い込んだり、勢いよく鼻をかむと、中耳炎の原因になることがあります。
- ゆっくり自然に洗い流し、やさしく鼻をかむようにしましょう。
3. 粘膜が荒れているとき・鼻づまりがひどいときは避ける
- 鼻の中が炎症を起こしているときや、強い鼻づまり・鼻血・痛みがあるときは使用を控えましょう。
- 無理に行うと症状が悪化する場合があります。そういった場合はまず耳鼻科に相談してください。
4. 1日1〜2回までを目安に
- やりすぎると、鼻の粘膜が乾燥して防御機能が低下してしまいます。
- 毎日の習慣にするなら、朝と就寝前の1日2回までが基本です。
予防と日頃のケア
- 花粉やPM2.5が多い日は帰宅後すぐ鼻うがい
- 朝晩の習慣化で鼻腔の清潔を保つ
- 就寝前に行えば後鼻漏による咳の予防に
- 洗浄液の温度は体温近くに(約37℃)
- 使用後の器具はよく洗い、乾燥させる
鼻洗浄を正しく習慣化することで、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎、慢性上咽頭炎の予防・再発防止に役立ちます。
さいごに
鼻うがいは、薬に頼らず自宅でできる優れたセルフケアです。
市販製品を活用すれば、誰でも簡単に始めることができます。
耳鼻科的にも科学的に効果が裏付けられており、鼻づまり、副鼻腔炎、上咽頭炎などの改善に有効です。
不安な点があれば、耳鼻科で相談し、正しい方法で習慣化することをおすすめします。