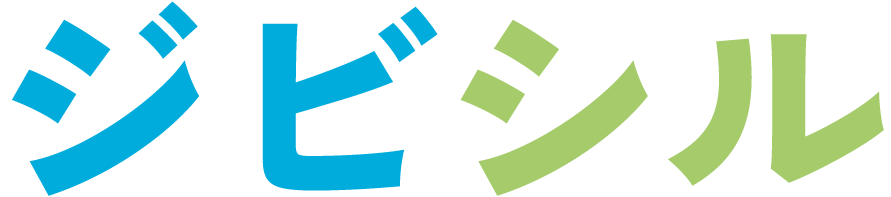高齢者に多く見られる「誤嚥性肺炎」は、食べ物や唾液が気道に入ってしまい肺に炎症が起こる病気です。症状が出るまで気づきにくく、重症化しやすいため注意が必要です。
- 誤嚥性肺炎とは、不顕性誤嚥に注意
- 初期症状が軽くても油断禁物
- 日々の口腔ケアが予防に効果的
早期発見・予防のカギは、「症状が出るまで」にどれだけ対策できるかにあります。以下で詳しくご紹介します。
誤嚥性肺炎の主な症状

誤嚥性肺炎の症状はゆっくりと進行することが多く、気づいたときには重症化していることも少なくありません。典型的な症状には以下があります。
- 微熱(37度台)や倦怠感が数日以上続く
- 食後の「むせ」や咳が増える
- 声がかすれる・湿ったような声になる
- 食欲低下や飲み込みづらさ
- 呼吸が浅く、ゼーゼーと音がする
特に「むせがなくても」誤嚥していることがあるため、不顕性誤嚥(silent aspiration)にも注意が必要です。
誤嚥性肺炎の原因・誤嚥性肺炎になり易い方
誤嚥性肺炎は、口腔内の細菌や食べ物、唾液が誤って気道に入り込むことで発症します。特に以下のような方はリスクが高まります。
- 高齢者(特に75歳以上)
- 脳血管障害・パーキンソン病など神経疾患を持つ方
- サルコペニア(嚥下筋の筋力低下)やオーラルフレイル(口腔機能の衰え)
- 夜間の嚥下反射が低下している方
- 慢性的な口腔ケア不足
高齢になると嚥下反射や咳反射が低下しやすく、症状が出るまで自覚しにくいのも特徴です。
誤嚥性肺炎の検査/診断方法

誤嚥性肺炎は、問診と身体診察、画像検査、嚥下機能の確認などで診断されます。
- 胸部レントゲン/CT検査:肺の炎症や影を確認します。
- 咽喉ファイバー検査:内視鏡を用いて嚥下の様子を直接観察。
- 改訂水飲みテスト(MWST)や反復唾液嚥下テスト(RSST):安全に水分を嚥下できるかの評価。
- 舌骨上筋群の筋力評価(GSグレード):首の筋力を評価。
診断は比較的短時間(15~30分程度)で完了し、早期に対応が可能です。
治療の方法・回復期間の目安
治療の基本は抗菌薬による感染症の治療と、嚥下機能の改善、リハビリテーションです。
- 抗菌薬投与:病原菌に応じて内服または点滴
- 嚥下リハビリ:口腔体操や呼吸筋トレーニング
- 口腔ケアの強化:歯磨き、舌清掃、保湿
軽症であれば外来治療で約1〜2週間、重症の場合は入院で2〜3週間かかることもあります。
類似症状の疾患
誤嚥性肺炎と似た症状を持つ疾患には、以下が挙げられます。
- 一般的な肺炎(細菌性/ウイルス性)
- 気管支炎
- 胃食道逆流症(GERD)
いずれも咳や微熱が見られますが、誤嚥性肺炎では「むせ」や「食後の咳」が特徴的です。
誤嚥性肺炎にならないための予防・日頃のケア

誤嚥性肺炎の予防には、日常の小さなケアが非常に重要です。
- 食後2時間はなるべく座位を保つ
- 1日2回以上の丁寧な口腔ケア(歯ブラシ+舌清掃)
- 口腔保湿・口腔リンスの活用
- 水分摂取をこまめに行う(脱水予防)
- 肺炎球菌ワクチンやBCGワクチンの接種
- 嚥下体操や発声練習(あいうべ体操 など)
特に「不顕性誤嚥」を防ぐために、口腔環境と嚥下機能の維持がカギです。
さいごに
誤嚥性肺炎は高齢者に多く、気づかないうちに進行するケースも少なくありません。
日々の口腔ケアと嚥下機能の維持、早期発見が重要です。
今までなかった「むせ」や咳が続くようなら一度医療機関に相談してみるのをおすすめします。