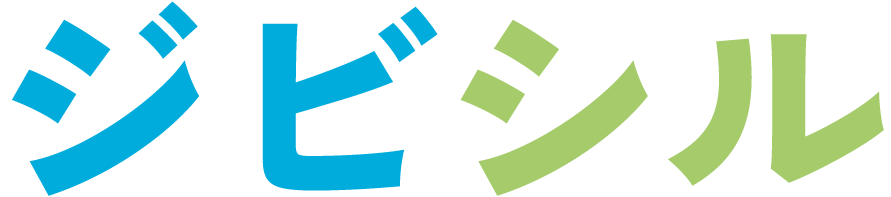耳が詰まった感じや、自分の声が響いて聞こえることはありませんか?それ、耳管開放症かもしれません。
耳管は本来、安静時には閉じており、嚥下やあくびの時に一時的に開きますが、この開放が持続してしまうのが耳管開放症です。ストレスや生活習慣が関係することもあり、症状が悪化すると仕事や日常生活に大きな影響を与えることもあります。
- ストレスが引き金になることも
- 自分に合った治し方を見つけよう
- コーヒーなどの習慣も見直しが必要
耳管開放症は日常生活の中のささいな要因が影響することがあります。最近では「鼻すすり型」や「隠蔽性耳管開放症」などの概念もあり、早期発見と正確な診断が重要です。
耳管開放症の主な症状
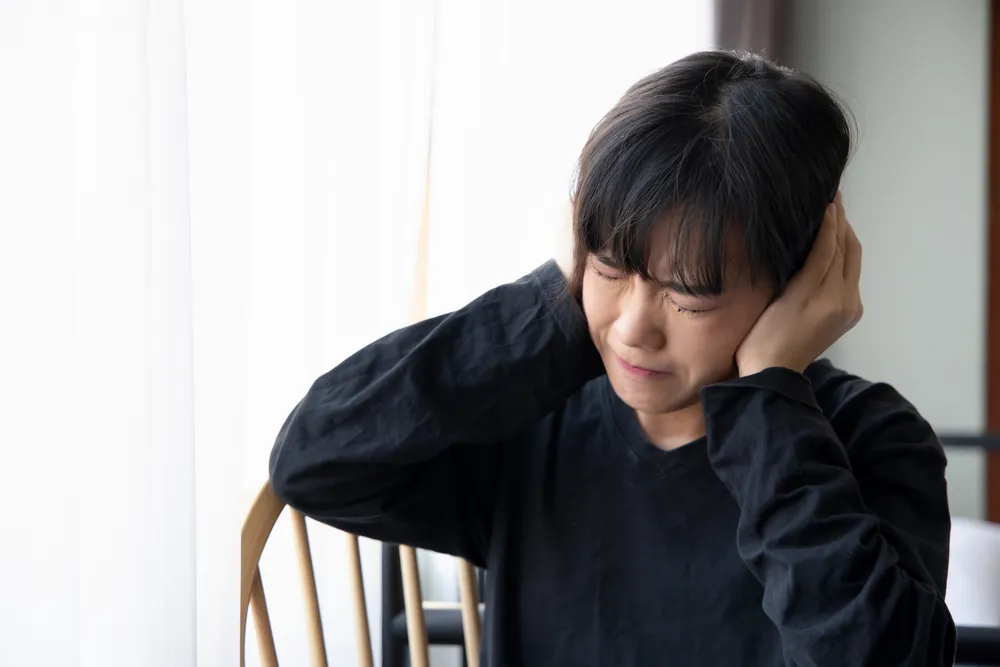
耳管開放症の主な症状には、以下が挙げられます。
- 耳が詰まった感じ(耳閉感)
- 自分の声が響いて聞こえる(自声強聴)
- 呼吸音が耳に聞こえる(自己呼吸音聴取)
- 症状が立位・座位で強く、臥位で軽減する
- 鼻すすりを頻繁に行うことで一時的に症状が緩和する例も
重症の場合、会話や発声が困難になり、精神的に不安定になる方もいます。
耳管開放症の原因・耳管開放症になり易い方

耳管開放症は耳と鼻をつなぐ耳管が持続的に開いた状態になる病気で、主な要因には次のようなものがあります。
- 急激な体重減少
- 自律神経の乱れ(ストレスや過労)
- 妊娠や更年期などホルモン変化
- カフェイン(コーヒーなど)の過剰摂取
- 鼻すすりの習慣化(鼻すすり型耳管開放症)
鼻すすりを繰り返すことで耳管が慢性的に軟らかくなり、「鼻すすり型耳管開放症」となるケースもあります。これは耳管が陰圧にロックされる現象を引き起こし、難治性の中耳疾患(真珠腫など)へ進行するリスクも指摘されています。
耳管開放症の検査/診断方法
耳管開放症の診断は、以下の症状や所見をもとに行います。
- 問診:症状が体位で変化する(臥位や前屈で軽快)
- 鼓膜の呼吸性動揺の観察(顕微鏡やファイバーで確認)
- 耳管機能検査(TTAG法や音響法)
- オトスコープを用いた聴診(ナ行の発声確認)
- CT検査(座位での画像診断が可能)
症状の重症度を評価するために、「PHI-10」という専用問診票を用いる場合もあり、これにより症状の程度や治療効果を客観的に把握することができます。
「鼓膜が動くか」「体位変化で症状が変わるか」が診断のカギで、上半規管裂隙症候群との鑑別も重要です。
治療の方法・回復期間の目安

治療は生活習慣の改善に加え、薬物療法や手術的処置が行われます。
- ストレス軽減、コーヒーの摂取制限
- 点鼻療法(生理食塩水を適切な方法で点鼻)
- 漢方薬(加味帰脾湯、補中益気湯など)
- スカーフ療法(ネクタイやスカーフを軽く締める)
- 鼻すすりを避ける指導
- 耳管ピン(限定施設で実施)、耳管口ジェル注入、鼓膜換気チューブ
改善の目安は1~2週間で症状軽快することもありますが、慢性化や重症例では1ヶ月以上かかる場合もあります。点鼻療法では、仰向けで頭を後ろに反らせ、患側を下にして点鼻するようにしましょう。保存的治療で改善しない難治例では、耳管ピン(Kobayashi Plug)を用いる手術療法が選択されることがあります。成功率は約75~80%とされますが、適応には慎重な判断が求められます。
類似症状の疾患
- 滲出性中耳炎
- 耳管狭窄症
- 上半規管裂隙症候群(体位で症状が軽快する点が似る)
誤診を避けるために、総合的な検査が必要です。
耳管開放症にならないための予防・日頃のケア
- ストレスの蓄積を避け、適度にリフレッシュ
- コーヒーなどカフェインの過剰摂取を避ける
- 急激なダイエットは控える
- 鼻すすりの癖がある場合は早期に指導を受ける
- 就寝時は頭をやや高くして臥位を利用する
さいごに
耳管開放症は見た目には分かりづらく、周囲の理解を得づらい症状です。ですが、正確な診断と早期の対応により、多くの方が快方に向かいますので、過度に心配せず気になったら耳鼻科医等に気軽にご相談ください。