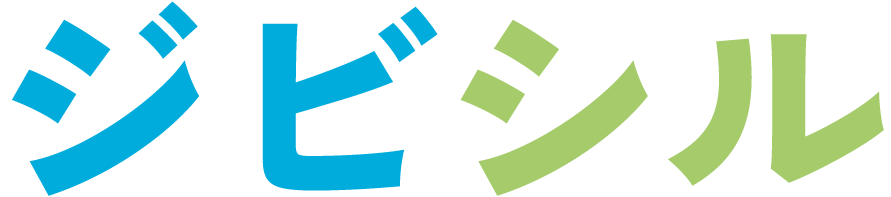毎年冬になると流行するインフルエンザ。
突然の高熱や全身のだるさに襲われ、「ただの風邪」とは明らかに異なる体調の悪さを感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
特にA型とB型の違いや、治療薬、感染期間、脳症などの重篤な合併症、後遺症などについては、誤解も多くあります。この記事では、インフルエンザに関する医学的エビデンスを基に、症状から治療、回復までを網羅的に解説します。
- A型・B型で症状や重症度に違いあり
- 感染期間は発症前から始まっている可能性も
- 薬の効果は服用のタイミングが鍵
インフルエンザを「正しく恐れる」ことが、重症化や合併症、そして後遺症のリスクを減らす第一歩です。
インフルエンザの主な症状と経過(発熱・関節痛・喉の痛み・鼻づまり)

インフルエンザは、38℃以上の高熱と共に、筋肉痛・関節痛、頭痛、全身倦怠感などの激しい全身症状で発症することが特徴です。発症は突然で、朝は元気だったのに夕方には動けなくなった、というような急激な経過をたどります。その後、咳、咽頭痛、鼻水、鼻づまりといった呼吸器症状が続きます。
特にA型では、高熱と強い全身症状が目立ちます。一方B型では、消化器症状(下痢・嘔吐・腹痛など)が前面に出るケースも少なくありません。消化器症状はウイルスの腸管への影響だけでなく、抗ウイルス薬(例:タミフル)や解熱剤の副作用としても現れることがあるため注意が必要です。
インフルエンザの治療薬まとめ
現在使用されている抗インフルエンザ薬には5つの主要な選択肢があります。
- オセルタミビル(タミフル):経口薬。5日間服用。A・B型に広く使用。
- ザナミビル(リレンザ):吸入薬。喘息患者には慎重投与が必要。
- ラニナミビル(イナビル):吸入薬。単回投与。吸入がうまくできない場合は効果が落ちる。
- ペラミビル(ラピアクタ):点滴薬。重症例や経口・吸入不可な場合に有効。
- バロキサビル(ゾフルーザ):新しい経口薬。1回で済む利便性があるが、耐性出現が課題。
これらはすべて、発症から48時間以内の投与で最も効果を発揮します。服用が遅れるとウイルス増殖を抑えきれず、重症化リスクや他者への感染リスクが高まるため、迅速な診断と処方が重要です。
解熱剤の正しい使い方と注意点(大人・子ども別)
解熱剤として推奨されるのはアセトアミノフェンです。これは小児から高齢者まで広く安全に使用できます。対して、NSAIDs(ジクロフェナク、イブプロフェン等)やアスピリンは、特に小児においてインフルエンザ脳症やライ症候群との関連が報告されており、使用は避けるべきです。
また、解熱剤は症状緩和のために使うもので、熱を無理に下げる必要はありません。特に発熱が身体のウイルス排除に役立つこともあるため、38.5℃を超える場合や、全身の苦痛が強い時に使用するのが望ましいとされています。
薬の副作用・下痢・倦怠感など体調不良への対応

インフルエンザ薬や解熱剤の副作用として、吐き気・下痢・腹痛・眠気・めまいなどが見られることがあります。とくにタミフルでは一部の小児に異常行動が報告されており、服用初期には注意深く見守る必要があります。
また、発熱が落ち着いた後に下痢が続く場合は、薬剤性かウイルスの影響か、あるいは二次感染かの鑑別が必要です。症状が長引く場合や強い倦怠感が残る場合は、医師に相談し適切な対処を受けましょう。
インフルエンザ脳症と後遺症:見逃してはいけないサイン
インフルエンザ脳症は、特に5歳以下の小児に起こりやすい重篤な合併症です。発熱後1〜2日以内に、以下のような症状が現れたら緊急受診が必要です。
- 意識障害(ぼーっとして反応しない)
- 異常行動(幻視、意味不明な言動)
- けいれん(特に繰り返す、長く続く)
脳症はサイトカインストーム(過剰な炎症反応)によるとされ、MRIで脳浮腫が認められることもあります。致死率は7~30%、生存しても知的障害やてんかんなどの後遺症が残ることが約25%とされています。早期発見・治療が鍵となります。
医療費・治療費の目安と保険適用範囲
インフルエンザの診察・検査・治療費の目安は以下の通りです。
- 診察料・検査費:約2,000〜3,000円(保険適用)
- 抗インフルエンザ薬:約1,000〜2,000円(保険適用)
自治体によっては、小児や高齢者に対する医療費助成がある場合もあります。また、民間保険に加入していれば、入院・通院に対して給付金が支払われることがあります。
回復を早める生活習慣(睡眠・水分・加湿)

回復には、十分な睡眠・安静、水分補給、室内の湿度管理(50〜60%が理想)が欠かせません。脱水を防ぐため、発熱中は1日1.5〜2リットルの水分をこまめに摂ることが推奨されます。
また、乾燥は喉や鼻粘膜を傷めて回復を遅らせるため、加湿器や濡れタオルの活用も有効です。食事は消化のよいもの(おかゆ・スープなど)を選び、無理な外出や仕事復帰は避けましょう。
耳鼻科で診られるインフルエンザ合併症(中耳炎・副鼻腔炎など)
特に小児では急性中耳炎、成人では副鼻腔炎を合併することがあり、インフルエンザ後の耳の痛みや鼻づまり、頭痛などが続く場合は耳鼻科受診を推奨します。
鼻の炎症が耳管を通じて中耳に波及したり、ウイルス性炎症が二次的に細菌感染に変わることで、抗生剤治療が必要になるケースもあります。耳鼻科では咽喉頭所見・鼓膜の観察・副鼻腔の評価などが可能です。
まとめ|早期受診と正しい治療が回復を左右する

インフルエンザは適切に対処すれば数日で回復することが多い一方、誤った判断や放置によって重症化や合併症、後遺症につながることもあります。特にA型・B型の違い、感染期間や解熱剤の選び方、薬の副作用、脳症とその早期サインを正しく理解することが重要です。
耳鼻科では合併症の有無を含めたトータルな診察が可能です。ご自身やご家族の体調に不安があるときは、迷わず医療機関へご相談ください。